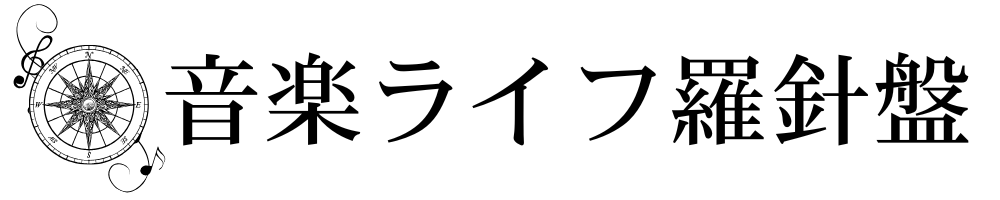はじめに:「音が重なると、もうお手上げ!」和声聴音の壁に挑むあなたへ
ピアノで「ジャーン!」と弾かれた和音…。 一番高い音(ソプラノ)や一番低い音(バス)はなんとなく追える気がするけど、**真ん中の音たち(内声)が、もはや団子状態で全然聴き分けられない…!**🍡😱
二声の課題ならまだしも、三声、四声と声部が増えた途端、頭の中が「???」で真っ白になっちゃう…。
聴音の授業で、和声課題の時間になると、途端に憂鬱な気分になる…。
楽典や和声の教科書で、コード進行や声部連結のルールは勉強したはずなのに、実際の音楽の響きと全然結びつかない…。
合唱やアンサンブルで、自分のパートを歌う(弾く)のに必死で、周りのパートがどう動いているかなんて、とてもじゃないけど聴き取れない…。
…こんな「和声聴音あるある」、あなたも身に覚えがありませんか?
わかります!わかりますとも!!😭 単旋律(メロディ)ですら難しいのに、複数のメロディライン(=声部)が同時に鳴る和声を正確に聴き取り、理解するなんて、まさにソルフェージュ・聴音学習における最大の壁の一つですよね!
でも、もし、その高く険しい壁を乗り越えて、複雑なハーモニーの響きの中から、各声部の美しい動きを聴き分けることができるようになったら…?
この記事は、「和声聴音、できるようになりたい!」と願う、向上心あふれるあなたのために書かれました!
この記事を最後まで読めば、あなたは…
- なぜ和声聴音が重要なのか、その意味とメリットがわかる!
- 難しい和声聴音を、二声→三声→四声と段階的に攻略していくための具体的な練習法がわかる!
- 多くの学習者がつまずく**「内声」を聴き取るための、とっておきのコツ**がわかる!
- ソルフェージュや聴音全体のレベルアップはもちろん、耳コピや作曲・アレンジにも役立つ耳が育つ!
- 和声の理論と実践が結びつき、音楽への理解が飛躍的に深まる!
「いやいや、私には無理だよ…特別な音感が必要なんでしょ…?」 そう思って諦めかけているあなた!ちょっと待ってください!
何を隠そう、この私も、昔は本当に和声聴音が苦手でした…。音大受験の聴音では、内声が全く聴き取れず絶望的な気持ちになったこともあります(遠い目)。何度練習しても四声体が聴き分けられなくて、「私には才能がないんだ…」と本気で落ち込んだことも…。
でも、断言します! **和声聴音能力は、決して一部の天才だけのものではありません!正しいアプローチで、段階的に、そして根気強くトレーニングを続ければ、必ず向上させることができるスキルなんです!**💪
この記事では、難しい音楽理論(楽典・和声学)の話も少し出てきますが、あくまで「聴き取る耳」を育てることに焦点を当て、
- なぜ和声聴音が大事なの?
- まずは何から始める?(二声の聴き取り)
- 三声・四声、そして難関の内声はどう攻略する?
- 具体的なトレーニングステップは?
- 理論の知識はどう活かせる?
といった内容を、私の失敗談(笑)も少し交えながら、初心者の気持ちにも寄り添いつつ、一つ一つ丁寧に解説していきます!
さあ、準備はいいですか? 複雑なハーモニーの謎を解き明かし、あなたの耳を「和声を聴き分ける耳」へと進化させる冒険へ、一緒に出発しましょう!🚀
第1章:和声聴音ってなぜ難しい?そして、なぜ重要?
「和声聴音」…なんだか字面からして、もうすでに難しそうなオーラが漂っていませんか?(笑) 「はじめに」でも触れたように、音楽学習者にとって大きな壁となることが多いこのトレーニング。
「正直、なんでこんな難しいことしなきゃいけないの?」 「単音とかメロディの聴き取りじゃダメなの?」
そんな風に思ってしまう気持ちも、よーくわかります。 でも、この一見すると複雑怪奇な和声聴音こそが、あなたの音楽への理解度を、ぐぐーんとネクストレベルへ引き上げてくれる、超・重要なスキルなんです!
この章では、まず「和声聴音」とは一体何なのかを改めて確認し、なぜ多くの人が「難しい!」と感じるのか、その理由を分析。そして、その困難を乗り越えた先に待っている、素晴らしいメリット(=重要性)について、熱く語っていきます!🔥
「和声聴音」とは?~複数のメロディライン(声部)を同時に聴き取る技術~
まず、「和声聴音(わせいちょうおん)」って何?という基本から。
超ざっくり言うと、 「複数の独立したメロディライン(=声部:せいぶ)が、同時に鳴っているのを耳で聴き取り、それぞれの声部の動きや、それらが全体として作り出すハーモニー(和音)を正確に理解する技術」 のことです。
「複数のメロディラインが同時…?」🤔
例えば、
- 合唱: ソプラノ、アルト、テノール、バスといった、4つの異なる声部が、それぞれ違うメロディを歌いながら、美しいハーモニーを作り出していますよね?あれを聴き取るのが、まさに和声聴音(四声聴音)です。
- ピアノ曲: 右手が奏でるメロディと、左手が奏でる伴奏(ベース音+和音)。これも、複数の声部が同時に鳴っていると捉えられます。
- オーケストラ: ヴァイオリン、フルート、トランペット、チェロ…たくさんの楽器が、それぞれ異なる動きをしながら、壮大なハーモニーを織りなしています。
このように、私たちが普段耳にする音楽の多くは、実は複数の声部が複雑に絡み合ってできているんです。和声聴音は、その複雑な音のタペストリーを、耳で解きほぐしていくような作業、と言えるかもしれませんね。
難易度が高い3つの理由
じゃあ、なんでこの和声聴音が、そんなに「難しい!」と感じられるのでしょうか?主な理由はこの3つ!
理由①:情報量が爆増!耳が大パニック!🤯
- 単音や単旋律なら、追うべき音は基本的に一つ。でも和声聴音では、2つ、3つ、4つ…と、同時に複数の音の情報を処理しなければなりません!耳に入ってくる情報量が、単純に何倍にもなるわけです。これじゃあ、耳がパニックになるのも無理はありませんよね💦
理由②:かくれんぼ名人!「内声」が聴こえない問題!🕵️♂️
- 和音の中で、一番高い音(ソプラノ)や一番低い音(バス)は、比較的聴き取りやすいことが多いです。これらを**「外声(がいせい)」**と呼びます。
- 問題は、その間に挟まれた**「内声(ないせい)」(アルトやテノールに相当するパート)!こいつらが、外声の響きに埋もれてしまって、めちゃくちゃ聴き取りにくいんです!まさに、かくれんぼ名人!この内声**をどう攻略するかが、和声聴音上達の大きなカギとなります。
理由③:耳だけじゃダメ?「和声」の知識も必要!🧠
- 和声聴音は、単に音が聴こえれば良い、というわけではありません。聴こえてきた音が、全体としてどんな和音(コード)を構成しているのか? その和音は次にどこへ進もうとしているのか? といったことを理解するには、ある程度の**「和声学(わせいがく)」(和音の連結ルールなどを学ぶ音楽理論**)や楽典の知識が必要になってきます。耳だけでなく、理論的な知識(頭)も使って分析する必要があるんですね。
うーん、こうして見ると、やっぱり難しそう…って思っちゃいますよね😅
でも、できるようになると世界が変わる!和声聴音のメリット
でもでも!諦めるのはまだ早い! この険しい山を乗り越えた先には、素晴らしい景色が待っているんです!和声聴音ができるようになると、こんなにもメリットが!
- メリット①:合唱・アンサンブル能力が劇的に向上! 自分のパートだけでなく、他の声部の動きや全体のハーモニーを感じながら演奏(歌唱)できるようになります。周りの音を聴く余裕が生まれ、より一体感のある、質の高いアンサンブルが可能に!まさに「耳が開く」感覚!
- メリット②:作曲・編曲における声部作成能力UP! 複数の声部が美しく、自然に流れるように書く技術(声部連結)は、作曲・編曲において非常に重要です。和声聴音で良い響きや流れをたくさん耳にすることで、その感覚が養われ、自分の作品にも活かせるようになります。引き出しが増える!
- メリット③:複雑な音楽構造の理解が深化! バッハのフーガのような対位法的な音楽や、オーケストラのように多くの楽器が複雑に絡み合う音楽も、各声部の動きやハーモニーの構造が聴き取れるようになると、その緻密さや美しさを、より深く味わうことができるようになります。
- メリット④:高度な耳コピ(パート別コピーなど)が可能に! 曲全体のコード進行はもちろん、ギターソロの裏で鳴っているバッキングパートや、ピアノの右手と左手の動き、合唱の各パートのラインなど、パートごとの動きを聴き取るような、高度な耳コピも夢ではなくなります!
難しいけれど、それに見合うだけの、いや、それ以上の価値が和声聴音にはあるんです!
ソルフェージュ学習における最終関門(?)の一つ
音楽の基礎訓練であるソルフェージュの学習プロセスにおいて、この和声聴音(特に四声体など)が、多くの場合、かなり高度なレベル、いわば「最終関門」の一つとして位置づけられていることを説明。
音楽の基礎訓練であるソルフェージュや聴音の学習プロセスにおいて、この和声聴音(特に三声や四声)は、多くの場合、かなり高度なレベル、いわば「最終関門」の一つとして位置づけられています。
単音 → リズム → 旋律 → 二声 → 和声(多声)…
というように、段階的に難易度が上がっていく中で、和声聴音は、これまでに培ってきた様々な聴音スキル(音高、音程、リズム、単旋律など)を総動員して挑む、いわば**「集大成」であり「最終関門」**の一つと言えるかもしれません。
だからこそ、挑戦しがいがあるし、乗り越えた時の達成感や、その先に広がる音楽の世界は、格別なものがあるんです!✨
難しいけど、やる価値は十分にある!むしろ、音楽を深く楽しむためには不可欠なスキルかも? さあ、その覚悟(?)ができたら、次章から具体的な攻略法を見ていきましょう!まずは基本の「二声」からです!
第2章:【基礎トレ】まずは「二声」から!外声(ソプラノ・バス)聴き取りのコツ
さあ、いよいよ和声聴音のトレーニング開始です! 第1章では、和声聴音がなぜ重要で、そしてなぜ難しいのか、その理由を探りましたね。(情報量の多さ、内声の聴き取りにくさ…などなど、手強い相手でした😅)
でも、ご安心を!いきなりラスボス(四声体とか!)に挑む必要はありません! 和声聴音のスキルアップは、段階的に進めていくのが鉄則!そして、その輝かしい第一歩となるのが、「二声(にせい)」、つまり2つの声部が同時に鳴っている音を聴き取るトレーニングなんです!
和声聴音の第一歩!なぜ「二声」から始めるのか?
「なんでいきなり三声とか四声じゃなくて、二声からなの?」 って思いますよね。それには、ちゃんと理由があるんです!
- 理由①:情報量がシンプル!: 当然ですが、声部の数が少ないので、耳で処理すべき情報量が比較的少なく、取り組みやすい!
- 理由②:ハーモニーの基本が掴める!: たった2つの音でも、重なり方(音程)によって響きは大きく変わります。この二声の響きを正確に捉えることで、基本的なハーモニーの感覚を養うことができます。
- 理由③:全ての土台になる!: 二声をしっかり聴き取れるようになれば、それが三声、四声と声部が増えたときの、聴き取りの大きな土台となります!
焦りは禁物!まずはこの二声という「基礎の基礎」をしっかりと固めることが、結果的に和声聴音マスターへの最短ルートになるんですよ!
最も聴き取りやすい!外声(がいせい)=ソプラノとバスに集中!
では、二声の聴き取り、具体的にどうやって進めればいいのでしょうか? ここで重要なポイントが、**「外声(がいせい)」**に意識を集中すること!
- 外声とは?: 複数の声部の中で、**一番高い音(最高声部=ソプラノ)**と、**一番低い音(最低声部=バス)**のことです。
<center>(イメージ:サンドイッチの一番上のパンと、一番下のパン)</center>
なぜ外声に注目するのか? それは、一般的に外声は、間に挟まれた内声(アルトやテノール)に比べて、人間の耳にとって聴き取りやすい傾向があるからです!
そして、このソプラノとバスの動きが、多くの場合、和音全体の響きやコード進行の骨格を形作っている、非常に重要なパートなんです!
だから、和声聴音の第一歩は、まずこの**「外声」=「ソプラノ」と「バス」の動きを、それぞれ正確に聴き取る**ことから始めましょう!
トレーニング①:ソプラノ(最高音)の旋律だけを追う練習
具体的なトレーニング方法です。まずは、二声の課題(音源や先生の演奏など)を聴きながら…
一番高い音、つまり「ソプラノ」のメロディラインだけを、意識して追いかけて聴き取る練習をします。
「あれ?これって、前の記事でやった『単旋律聴音』と同じじゃない?」 と思ったあなた、その通り!鋭い!👏
これは、下の声部(バス)の音は一旦BGMのように捉え、ソプラノのメロディだけに集中する練習です。旋律聴音の良い復習にもなりますし、「複数の音が鳴っていても、特定の声部だけを抜き出して聴く」という、和声聴音に必要な基本的な耳の使い方のトレーニングになります。
**「下の音は気にしない!キラキラしたソプラノの歌声だけを追いかけるぞ!」**という気持ちで!✨
トレーニング②:バス(最低音)の旋律だけを追う練習
ソプラノが聴き取れるようになったら、今度は逆!
一番低い音、つまり「バス」のメロディライン(ベースライン)だけを、意識して追いかけて聴き取る練習をします。
ベースラインは、音楽の土台となる、非常に重要なパート。コードの響きを決定づけたり、コード進行の流れを作ったりする上で、大きな役割を果たしています。
「今度は上のソプラノは無視!どっしりとしたバスの動きに集中だ!」という感じで、低い音域の動きに耳を澄ませてみてください。ベースラインが聴き取れるようになると、音楽全体の安定感や進行感が掴みやすくなりますよ!듬직(ドゥムジク:頼もしい)!
トレーニング③:ソプラノとバスの「音程関係」を意識して聴く
ソプラノとバス、それぞれの声部の動きを個別に聴き取れるようになったら、いよいよ次のステップ!
ソプラノとバスが「同時に」鳴っている瞬間の、「音程関係(ハーモニー)」を意識して聴く練習です。
- 「この瞬間、ソプラノの『ミ』とバスの『ド』が鳴ってるな…音程は『長3度』か」
- 「ここではソプラノ『レ』とバス『ソ』…これは『完全5度』だな、安定してる響きだ」
- 「お、ここはソプラノ『ファ』とバス『シ』…これは『増4度』!不安定な響き!」
というように、二声が作り出す縦の響き(ハーモニー)にも注目していくのです。 これにより、単に2つのメロディを追うだけでなく、それらが合わさった時の**「響きそのもの」を感じ取る耳**が養われていきます。これが、和声聴音の核心に近づくための重要なステップです!
二声の動きのパターン(反行・並行・斜行)を意識すると聴きやすくなる?
(これは少し発展的なヒントですが…) 二声のメロディがどのように動いていくかには、いくつかの基本的なパターンがあります。専門用語では「声部進行」と言います。
- 反行(はんこう): 2つの声部が、互いに反対方向に動くこと。(例:ソプラノが上がる時、バスは下がる)→ 響きが豊かになりやすい。
- 並行(へいこう): 2つの声部が、同じ音程を保ったまま、同じ方向に動くこと。(例:ソプラノがド→レと上がる時、バスもファ→ソと上がる)→ 多用すると響きが単調になることも。(※特に完全1・5・8度の連続並行は、古典的な和声では基本的に避けられます)
- 斜行(しゃこう): 一方の声部が動き、もう一方は同じ音に留まること。(例:ソプラノがド→レと上がる時、バスはずっとソのまま)
これらの動きのパターンを知っておくと、二声の聴音をする際に、「あ、ここは反行してるな」「今は並行だ」というように、動きを予測したり、分析したりするヒントになることがあります。余裕があれば、頭の片隅に置いておくと良いかもしれません。(今は「ふーん」でOK!)
まずはこの二声の骨組みをしっかり聴き取る耳を育てることが、和声聴音攻略の第一歩です! 基礎が固まったら、いよいよ難関「内声」を含む三声・四声の聴き取りに挑戦しましょう!
第3章:【ステップアップ】「三声・四声」へ!難関「内声」聴き取り攻略法
第2章では、和声聴音の第一歩として、比較的聴き取りやすい**「二声」、特に外声**(ソプラノとバス)の聴き取りのコツと練習法を学びましたね!2つの声部の動きや響き、少しずつ掴めるようになってきたでしょうか?😊
さあ、基礎が固まってきたところで、いよいよ本格的な山の登頂へ!次は声部が3つ、4つと増える**「三声(さんせい)」、「四声(よんせい:ソプラノ・アルト・テノール・バス)」の和声聴音**に挑戦です!
…と意気込んだものの、 「うわっ!声部が増えた途端、音が団子になって、何が何だか…!😭」 「ソプラノとバスは追えるけど、中の音(内声)が全然聴こえない!」
そうなんです!声部の数が一つ、二つ増えるだけで、和声聴音の難易度は、体感的にぐぐーんと跳ね上がります!ここが、多くの学習者がつまずきやすい、大きな壁なんですよね…。
でも、大丈夫!この章では、その高い壁を乗り越えるための鍵となる、特に難しい「内声」の聴き取り攻略法を中心に、三声・四声聴音へのアプローチを解説していきます!
声部が増えると難易度急上昇!三声・四声聴音の壁
なぜ三声、四声と声部が増えると、そんなに難しくなるのでしょうか?
- 情報量がさらに増える!: 当然ながら、同時に処理すべき音の情報が、二声の時よりもさらに多くなります。耳と脳が大忙し!🧠💦
- 音が密集して混ざり合う!: 特に四声体の場合、ソプラノ・アルト・テノール・バスの4つの音が、時には近い音域で重なり合い、それぞれの声部の輪郭がぼやけて聴き取りにくくなります。
特に、ピアノで弾かれる四声体の和声課題(音楽大学の入試などでもよく出題されます)は、ソルフェージュ学習における大きな山場の一つと言えるでしょう。
なぜ「内声(ないせい:アルト・テノール)」は聴き取りにくいのか?
そして、三声・四声聴音で、多くの人を悩ませる最大の難関が、「内声(ないせい)」、つまり**中間の声部(アルトやテノールに相当するパート)が聴き取れない!**という問題です。
内声がまるで忍者🥷のように気配を消して、私たちの耳から隠れてしまうのには、いくつかの理由があります。
- 音量の問題: 一般的に、一番高いソプラノと一番低いバス(外声)がメロディラインや和音の土台として強調されることが多く、内声はそれらに比べて音量が小さめに演奏されたり、響きの中に埋もれてしまったりしがちです。
- 動きの少なさ: 曲によっては、内声は外声ほど活発に動かず、同じ音を保持したり、単純な動きを繰り返したりすることがあります。動きが少ないと、耳がその存在を捉えにくくなるんですね。
- 音域的な問題: 内声が存在する中音域は、他の声部と音が重なりやすく、響きが混濁しやすい音域でもあります。
うーん、こう聞くと、ますます内声聴き取り、難攻不落な感じがしますよね…。 でも、諦めるのはまだ早い!ちゃんと攻略法はあるんです!
内声聴き取りのコツ①:急がば回れ!まず外声(ソプラノ・バス)を確定させる!
「内声が聴こえないなら、内声を集中して聴けばいいんでしょ?」 …と、焦って内声ばかりを追いかけようとするのは、実は逆効果なことが多いんです!
内声聴き取り攻略の鉄則、それは…
「まず、聴き取りやすい外声(ソプラノとバス)を確実に聴き取り、それを『手がかり』にする!」
です!まるで、建物の土台(バス)と屋根(ソプラノ)を先にしっかりと作ってしまうようなイメージですね。
【なぜ外声が手がかりになる?】
- 全体の響きの輪郭が決まる: 外声の動きと響きがわかれば、その間に挟まれる内声が動きうる範囲や、全体の和音の種類がある程度限定されてきます。
- 推測の精度が上がる: 外声と内声が組み合わさって、特定の和音(例えばCメジャーコード=ドミソ)が作られているはずなので、「ソプラノが『ミ』でバスが『ド』なら、内声は『ソ』の可能性が高いな…」というように、和声の知識(コード構成音)を使って内声の音を推測しやすくなります。
焦って内声を聴こうとする前に、まずは落ち着いて、確実に聴き取れる外声をしっかりと捉え、できれば記譜してしまう。これが、結果的に内声攻略への一番の近道となることが多いんですよ!「急がば回れ」ですね!
内声聴き取りのコツ②:和音の「響き(種類)」から内声を推測する!
コツ①と連携するアプローチですが、外声だけでなく、**その瞬間に鳴っている「和音全体の響き(種類)」**も、内声を特定するための大きなヒントになります。
例えば…
- 聴こえてきた和音が、全体として**「明るくて安定した響き(メジャーコードっぽい)」**と感じたとします。
- そして、外声がソプラノ「ソ」、バス「ド」だと聴き取れたとします。
- この場合、メジャーコード(長三和音)の構成音は「根音・長3度・完全5度」なので、ルートが「ド」なら「ド・ミ・ソ」のはず。
- ということは…? 「内声はきっと『ミ』の音だろう!」と推測できるわけです!
もちろん、転回形(ベース音がルート以外の音)や非和声音(和音の構成音以外の音)など、複雑なケースもありますが、基本的な和音の種類とその響きの特徴(第2章・第3章で学びましたね!)を知っていれば、このように全体の響きから内声を推理することが可能になります。耳だけでなく、頭(和声の知識)も使って内声の正体に迫りましょう!
内声聴き取りのコツ③:声部連結(つながり)の自然な流れを意識する
音楽(特に和声)では、各声部は、前の音から次の音へ、できるだけ**「自然で滑らかに」繋がるように動くのが基本とされています(これを「声部連結(せいぶれんけつ)」と言います)。特に内声**は、外声ほど大きく跳躍することは少なく、**順次進行(隣の音に進む動き)**や、同じ音を保つ動きが多く見られます。
この**「声部連結の自然さ」を意識することも、内声を聴き取る**上で役立ちます。
- 「この内声、前の音からいきなり1オクターブも跳躍するのは、ちょっと不自然じゃないかな?」
- 「前の音が『レ』だったから、次の音は順次進行で『ド』か『ミ』の可能性が高いな」
というように、**音楽的な「流れ」や「自然さ」**を考慮することで、聴き取りの候補を絞り込んだり、間違いに気づいたりすることができるんです。内声だって、ちゃんと「歌っている」はず!その歌の流れを感じ取ってみましょう。
内声聴き取りのコツ④:苦手な声部(アルトorテノール)に集中して聴く練習
最終的には、やはり特定の声部に意識をフォーカスして、繰り返し聴く練習が不可欠です。
特に内声は、アルトとテノールの2つの声部がありますよね(四声の場合)。
- 「今日はアルト(ソプラノのすぐ下の声部)の動きだけを集中して追ってみよう!」
- 「次はテノール(バスのすぐ上の声部)だけに耳を澄ませてみよう!」
というように、ターゲットを絞って、その声部のメロディラインを追いかける練習をします。 最初は、他の音に埋もれて微かにしか聴こえないかもしれません。でも、根気強く、意識を集中させて聴き続けることで、だんだんその声部の輪郭が浮かび上がってくるようになります。まるで、ラジオのチューニングを合わせるような感覚に近いかもしれませんね。📻
内声攻略は和声聴音の山場ですが、これらのコツを駆使すれば必ず道は開けます! 次章では、これらのコツを踏まえた上で、具体的な和声聴音のトレーニングステップを見ていきましょう!
第4章:実践トレーニング!和声聴音の具体的な練習ステップ
さあ、和声聴音の理論武装(?)は整いましたね!知識とコツをインプットしたら、次はいよいよそれを実践で活かし、あなたの「耳」を本格的に鍛え上げる番です!
「でも、具体的に何から手をつければいいの?」 「どんな順番で練習すれば、効率よくレベルアップできる?」
そんな疑問に答えるために、この章では、和声聴音のトレーニングを独学でも進められるような、具体的な練習ステップを順を追ってご紹介します!
練習の進め方:簡単な課題から段階的にレベルアップ!
まず大前提として、和声聴音のような複雑なスキルは、いきなり難しい課題に挑戦しても、心が折れてしまうだけです…(経験者は語る😅)。
大切なのは、**「簡単な課題から始めて、少しずつ難易度を上げていく」**という、段階的なアプローチ!
- 声部の数: まずは二声 → 慣れたら三声 → そして最終目標の四声へ!
- 和音の種類: 単純な三和音(メジャー、マイナー)中心 → 七の和音(セブンスコード)や転回形、非和声音を含むものへ!
- リズム: シンプルなリズム → 付点リズムやシンコペーションなど複雑なリズムへ!
- 課題の長さ: 短い2~4小節 → 8小節、16小節…と徐々に長く!
- テンポ: ゆっくりなテンポ → 少しずつ速いテンポへ!
このように、スモールステップで「できた!」という成功体験を積み重ねていくことが、モチベーションを維持し、着実にスキルアップするための秘訣です!焦らず、自分のペースで進めていきましょうね!
ステップ1:短い(2~4小節)課題から始める
まずは、ウォーミングアップ!2~4小節程度の、ごく短い和声聴音の課題から始めましょう。
【なぜ短い課題から?】
- 集中力が続く!: 長い課題だと、途中で集中力が切れてしまいがち。短い課題なら、最後まで集中して音を聴くことができます。
- 記憶しやすい!: 短いフレーズなら、音の動きや響きを記憶に留めやすいです。
- 達成感を得やすい!: 短い課題なら、クリアする回数も増え、「できた!」という達成感を感じやすく、モチベーションに繋がります。
短い課題といえども、和声聴音の重要な要素(声部の動き、ハーモニーの響き)はちゃんと詰まっています。まずは短い距離を確実に走りきる練習から始めましょう!
ステップ2:まずはリズムを無視して「和音の響き」だけを捉える練習
課題を聴く際、いきなりリズムや細かい音符まで完璧に聴き取ろうとすると、情報量が多すぎてパニックになりがちです。
そこで、最初の数回は、リズムは一旦置いておいて、各拍(あるいは各和音)で鳴っている「和音全体の響き」そのものに集中する練習がおすすめです。
【意識するポイント】
- コードの種類: 「ここはメジャーっぽい明るい響きだな」「ここはマイナーセブンスの切ない感じだ」など、第2・3章で学んだ和音のキャラクターを感じ取ります。
- 響きの変化: 和音が移り変わる(コードチェンジする)タイミングと、その響きがどう変化したか(明るくなった?暗くなった?不安定になった?)を捉えます。
- 転回形?: ベース音(最低音)がルート音(根音)ではない「転回形」の響きにも、少しずつ耳を慣らしていきましょう。(これは少し応用)
リズムは後からでも当てはめられます。まずは、ハーモニーの「色彩感」や「雰囲気」を大まかに掴むことに集中してみましょう!
ステップ3:外声(ソプラノ・バス)の旋律を書き取る
和音全体の響きのイメージが掴めてきたら、次は聴き取りやすい**「外声(ソプラノとバス)」のメロディ**ラインを、楽譜に書き出す(記譜する)ステップです。
【進め方】
- 第2章のトレーニング①②を思い出し、まずはソプラノ(最高音)の動きだけを集中して聴き取り、リズムも意識しながら記譜します。(旋律聴音のスキルが活きますね!)
- 次に、バス(最低音)の動きだけを集中して聴き取り、同様に記譜します。
この段階で、楽譜には一番上の段(ソプラノ)と一番下の段(バス)の音符が書き込まれている状態になります。これで、和声全体の「骨組み」が見えてきましたね!
ステップ4:内声(アルト・テノール)を推測・聴き取り、書き加える
さあ、いよいよ難関の**「内声(アルト・テノール)」**の攻略です!
【進め方】
- 推測する!: ステップ3で書き出した外声と、ステップ2で掴んだ和音全体の響き(種類)を手がかりに、「この和音を構成するためには、内声はどんな音が鳴っているはずか?」と推測します。(第3章のコツ②を活用!)
- 集中して聴き取る!: 推測した音を念頭に置きながら、課題をもう一度聴き、アルト(ソプラノのすぐ下)の動き、テノール(バスのすぐ上)の動きに、それぞれ意識を集中させて聴き取ります。(第3章のコツ④)
- 声部連結を意識する!: 聴き取った(あるいは推測した)内声の音が、前後の音と自然に繋がっているかも意識しましょう。(第3章のコツ③)不自然な跳躍は少ないはずです。
- 書き加える: 聴き取れた内声の音を、対応するリズムに合わせて、楽譜の中間の段に書き加えていきます。
最初は推測がメインになってしまうかもしれません。でも、それでOK!練習を重ねるうちに、だんだんと実際に聴こえる内声の音が増えてくるはずです。根気強く!
ステップ5:声部連結や和声進行を確認・修正する
全ての声部(二声なら2つ、四声なら4つ)を書き終えたら、最後の仕上げ!必ず全体を見直して、確認・修正しましょう。
【チェックポイント】
- 拍数は合ってる?: 各小節の拍数の合計が、拍子記号と一致しているか?(超基本!)
- リズムは合ってる?: 各声部のリズムは、聴き取った通りに書けているか?
- 音高は合ってる?: 各声部の音の高さは正しいか?臨時記号(♯♭♮)の付け忘れはないか?
- 声部連結は自然?: 各声部の動きが、極端に跳躍したり、不自然な動きをしたりしていないか?(和声学のルールを知っていると、より細かくチェックできます)
- 全体の響きは合ってる?: 書き出した楽譜を頭の中で鳴らしてみたり、可能なら楽器で弾いてみたりして、元の課題の響きと一致しているか確認!
間違いを見つけたら、なぜ間違えたのかを考えながら修正します。この作業を通して、あなたの聴音力と記譜力は着実に向上していきます!
【重要】答え合わせと分析:なぜ間違えたのか?を徹底的に考える
和声聴音のトレーニングにおいて、最も重要なプロセスと言っても過言ではないのが、
「答え合わせ」と「間違えた箇所の分析」
です!
【なぜ重要?】
- 自分の弱点がわかる!: 答えと照らし合わせることで、「自分は内声の聴き取りが特に苦手だな」とか「この和音の響きを勘違いしていたな」「このリズムパターンをよく間違えるな」といった、具体的な弱点や課題が明確になります。
- 原因を考えることで次に繋がる!: なぜ間違えたのか?(単なるケアレスミス? 音程の認識違い? リズムの勘違い? 和声知識の不足?)その原因を深く考えることで、次に同じ間違いを繰り返さないための対策を立てることができます。
- 正しい響きを再確認できる!: 正解の楽譜を見て、もう一度音源を聴き直すことで、「ああ、この響きが正解だったのか!」と、正しい音と楽譜を結びつけて記憶することができます。
**答え合わせをして、間違っていたら「あーあ」で終わらせるのではなく、「なぜ間違えたんだろう?」と徹底的に分析すること。**これこそが、和声聴音能力を確実に向上させるための、一番の近道であり、王道なのです!間違いは成長のタネ!🌱
地道な作業ですが、このステップを丁寧に繰り返すことで、あなたの耳は確実に和声を捉えるようになります! 次章では、さらに聴き取り精度を上げるための「理論活用術」をご紹介します!
第5章:【理論活用】和声学・楽典の知識で聴き取り精度を上げる!
第4章では、和声聴音の具体的なトレーニングステップをご紹介しましたね!耳を鍛えるトレーニング、頑張っていますか?😊
実は、そのトレーニング効果をさらに高めるための「秘密兵器」があるんです…それは、あなたの**「頭脳」、つまり「音楽理論(和声学・楽典)」の知識**なんです!
「えー!また難しい理論の話!?😱」 って思ったあなた、ちょっと待ってください!ここで言う「理論」は、決して小難しいお勉強の話ではありません。あなたの「耳」を助け、和音の響きをより深く理解するための、**超・実践的な「ヒント」や「考え方」**のことなんです!
「耳」だけに頼るのではなく、「頭(理論)」も上手に使うことで、和音聴き分けの精度とスピードは格段にアップします!さあ、その具体的な活用術を見ていきましょう!
理論を知れば耳も育つ!楽典・和声の知識を聴き取りに活かす
なぜ音楽理論の知識が和音の聴き分けに役立つのでしょうか?
それは、音楽(特に西洋音楽)の多くは、ある程度予測可能な「パターン」や「ルール」に基づいて作られていることが多いからです。理論を知っていると…
- 「この和音の後には、次はこういう響きの和音が来やすいな」
- 「この曲の雰囲気からすると、ここで使われているのはあの種類の和音っぽいぞ」
- 「このメロディの動きに対して、自然に響くのはこのコードだな」
…というように、闇雲に音を聴き取るのではなく、理論的な裏付けを持って「あたり」をつけたり、響きを確認したりできるようになるんです!まるで、推理小説を読むときに、伏線を知っていると犯人が予測しやすくなるようなものですね🕵️♂️。
では、具体的にどんな知識が役立つのか、4つの活用術をご紹介します!
活用術①:和音の「機能(トニック/ドミナント/サブドミナント)」と連結パターンを知る
音楽理論(特に和声学)では、和音にはそれぞれ**「機能(役割)」**があると考えます。主なものは以下の3つでしたね。(第1章でも少し触れました)
- トニック (Tonic / T): 「安定」「落ち着き」「ホームベース」。曲の始まりや終わりによく使われる、安心感のある響き。(例:メジャーキーならⅠの和音、マイナーキーならⅠmの和音など)
- ドミナント (Dominant / D): 「不安定」「緊張感」「トニックに進みたい!」。曲の盛り上がりや、終止(終わり)の直前によく使われる、強い引力を持つ響き。(例:Ⅴ7の和音=ドミナントセブンス!)
- サブドミナント (Subdominant / SD): 「少し不安定」「展開」「トニックにもドミナントにも進める」。曲に彩りや変化を与える響き。(例:Ⅳのコード、Ⅱmのコードなど)
そして、これらの機能を持つ和音は、**ある程度決まったパターンで連結(繋がっていく)ことが多いんです。(これを「コード進行」や「和声進行」**と言います)
例えば、最も基本的な進行パターンの一つが「T → (SD) → D → T」。 「安定した場所から出発し、(ちょっと寄り道して)、一番緊張感のある場所へ行き、最後にまた安定した場所へ帰ってくる」という、音楽の基本的なストーリー展開を表しています。
この**「機能」と「典型的な連結パターン」**を知っていると、和声聴音の際に、
「あ、ここはドミナント(D)の響きがするぞ…ということは、次はきっとトニック(T)に進むはずだ!」 「この部分はサブドミナント(SD)っぽいな。次はドミナント(D)か、あるいはトニック(T)に戻るかな?」
というように、コード進行全体の流れを予測しながら聴き取ることができるようになります!音楽の文法を知ることで、文脈から答えを推測しやすくなるんですね!
活用術②:和音の「転回形」の響きの違いを理解する
和音は、構成音のどの音が一番下(ベース音)に来るかによって、「基本形」と「転回形(てんかいけい)」に分かれます。(これも楽典の知識ですね!)
例えば、Cメジャーコード(ドミソ)なら…
- 基本形: ベース音が「ド」(ルート音)→ ド・ミ・ソ (一番安定した響き)
- 第一転回形: ベース音が「ミ」(第3音)→ ミ・ソ・ド (少し軽やかな響き)
- 第二転回形: ベース音が「ソ」(第5音)→ ソ・ド・ミ (少し不安定で、次に進みたがる響き)
このように、同じ和音でも、転回形になると響きの印象が少し変わります。 この転回形による響きの違いを知っておくと、和声聴音の際に、
「この和音、メジャーっぽいけど、ベース音がルートじゃないな…もしかして転回形?」 「この不安定な響きは、第二転回形かもしれないぞ?」
というように、聴こえてきた和音の種類だけでなく、その**「形(転回形か基本形か)」まで識別する手がかりになります。特にベース音との関係性**に注目すると、転回形は見抜きやすいですよ!
活用術③:「非和声音(ひわせいおん)」の種類と響きを知る
音楽の中では、常に和音の構成音だけが鳴っているわけではありません。メロディや内声には、和音の構成音以外の装飾的な音、いわゆる**「非和声音(ひわせいおん)」**が、スパイスのようにたくさん使われています。
非和声音にも色々な種類があります。(これも楽典の範疇です)
- 経過音: となりの和音構成音へスムーズに繋ぐ音(例:ド・レ・ミ の「レ」)
- 刺繍音: 和音構成音から一時的に隣の音へ行ってすぐ戻る音(例:ド・レ・ド の「レ」)
- 倚音(いおん): 強拍で和音構成音にぶつかって(不協和)、次に解決する音
- 掛留音(けいりゅうおん): 前の和音の音が残り、次の和音とぶつかってから解決する音
…などなど。(全部覚える必要はありませんよ!)
これらの非和声音の存在と、よく使われるパターンや響きを知っておくと、和声聴音中に和音の構成音以外の音が聴こえてきても、
「あ、これは経過音だな」 「今の不協和音は、倚音っぽいぞ」
と、冷静に分析することができます。非和声音の存在を知らないと、「あれ?何の音だこれ?コード間違えた?」とパニックになってしまいがちですが、知識があれば、聴き取りの際の混乱を減らすことができるんです!
活用術④:カデンツ(終止形)のパターンを覚える
「カデンツ(終止形)」とは、音楽のフレーズや曲の区切り、終わりによく使われる、定型的なコード進行のパターンのことです。(これも和声学の重要ターム!)
代表的なカデンツには、以下のようなものがあります。
- 完全終止: Ⅴ(7) → Ⅰ (ドミナント→トニック)。最も強い終止感・解決感を持つ。「終わったー!」という感じ。
- 偽終止(ぎしゅうし): Ⅴ(7) → Ⅵm など、トニック以外の和音に進む。「あれ?終わると思ったら、まだ続くの?」という意外性。
- 半終止: Ⅳ → Ⅴ や Ⅱm → Ⅴ など、ドミナントで一旦停止する。「まだ続くよ!」という中間地点の感じ。
- アーメン終止(変終止): Ⅳ → Ⅰ (サブドミナント→トニック)。賛美歌などでよく使われる、穏やかな終止感。
これらの典型的なカデンツのパターンと、それぞれの響きの特徴を覚えておくと、曲の区切りや終わり際で、
「あ、この響きは完全終止っぽいな!」 「ここは半終止のパターンだ!」
というように、コード進行を聴き取る上で、非常に大きな手がかりになります!音楽の「定型句」を知っておくようなものですね。
理論学習と聴音トレーニングを連携させて相乗効果を狙おう!
ここまで見てきたように、音楽理論(和声学・楽典)の知識は、和声聴音の聴き取り精度を上げるための強力な武器となります。
ですから、和声聴音の能力を効率的に高めたいなら、
「耳」を鍛える聴音トレーニングと、「頭」を使う理論学習を、並行して進めていくこと
が、非常に効果的です!
- 聴音で聴こえてきた響きを、「これは理論でいう〇〇だな」と頭で確認する。
- 理論で学んだコード進行やルールを、「実際にどんな響きがするんだろう?」と耳で確認する。(特に自分で楽器を弾いてみるのがベスト!)
この**「耳⇔頭」の連携プレー、往復運動を繰り返すことで、あなたの音楽**に対する理解は、知識だけでも、感覚だけでも得られない、より深く、より確かなものへと進化していくはずです!
難しい理論書とにらめっこするだけでなく、常に実際の「音」を聴きながら、響きを確かめながら学ぶ姿勢を大切にしてくださいね!
耳と頭、両方をバランスよく使って、和声聴音の壁を乗り越えましょう! あなたの音楽の世界は、もっともっと深く、豊かになるはずです! さあ、最後のまとめで、あなたの冒険を締めくくりましょう!
まとめ:和声聴音は根気!でも乗り越えれば音楽の世界がさらに深まる!
いやはや、和声聴音マスターへの長く険しい道のり、本当によくぞここまでたどり着きました!全5章、本当にお疲れ様でした!🍵 そして、ありがとうございます!🙏
「ジャーン!」と鳴る和音の響き、二声から三声、四声へと重なる音のタペストリー…。この記事を読む前と比べて、その複雑な響きの中から、少しでも多くの情報を聴き取るための道筋やヒントが見えてきたでしょうか?
「内声、やっぱり難しいけど、攻略法はわかったぞ!」 「和声の理論と耳を結びつけるって、こういうことか!」 「トレーニング、地道だけど頑張ってみようかな!」
そんな風に、和声聴音への苦手意識が少しでも和らぎ、前向きな気持ちになっていただけていたら、ナビゲーターとして、これ以上の喜びはありません!✨
最後に、この険しい山を登るための「登山ガイド」=和声聴音攻略のポイントを、ぎゅぎゅっと凝縮しておさらいしましょう!
【和声聴音マスター登山ガイド:要点まとめ】
- なぜ登る?: 難しいけど超重要!音楽理解、演奏力、作曲力…あらゆるスキルUPの鍵!(第1章)
- まずは麓から: 二声聴音からスタート!外声(ソプラノ・バス)を確実にキャッチ!(第2章)
- 難所・内声攻略!: 外声を手がかりに、響き・連結・集中力で挑む!諦めない!(第3章)
- 実践登山ステップ: 短い課題→響き→外声→内声→確認&分析!答え合わせが命!(第4章)
- 秘密兵器!理論活用: 和声学・楽典(機能/転回形/非和声音/カデンツ)の知識で耳を助ける!(第5章)
そう、和声聴音は、ソルフェージュや聴音の中でも特に難易度が高いスキルです。一朝一夕にマスターできるものではありません。時間もかかるし、根気もいります。
でも、それは決して「才能」だけで決まるものではなく、**正しい方法で、段階的に、そして継続的にトレーニングすれば、誰でも必ず向上させることができる「技術」**なんです!
そして、このスキルを身につけることで、あなたは音楽の表面的なメロディだけでなく、その奥にあるハーモニーの色彩、声部間の美しい対話、音楽全体の構造的な美しさを、より深く感じ取ることができるようになります。
それは、まるで白黒テレビがカラーテレビになるような、あるいは、普段見ている景色の解像度が、一気に4Kになるような…そんな**「世界が変わる」**体験なんです!
さあ、知識と方法という登山装備を身につけたあなた!今日からできる一歩で、和声聴音の山に再挑戦してみませんか?
- まずは簡単な二声の課題を、ソプラノだけ、バスだけ、と分けて聴く練習からリスタート!
- 聴音アプリを使って、メジャーコードとマイナーコードの聴き分けに加えて、ドミナントセブンスの響きも覚える練習をしてみませんか?
- 和声学の教科書(あるいはネットの情報)で「コード機能」について少し読んでみてから、好きな曲のコード進行を聴いてみませんか?
焦らなくて大丈夫。大切なのは、諦めずに、少しずつでも耳を和声に触れさせ続けること。そして、何より**「楽しむ気持ち」**を忘れないこと!
和声聴音の壁は、確かに高いです。私も、何度も何度もぶつかり、心が折れかけました(笑)。でも、少しずつでも聴こえる声部が増えていく感覚、和音の響きの違いがわかるようになった時の感動は、その苦労を吹き飛ばしてくれるほどのものです。
この記事が、あなたがその高い壁を乗り越え、音楽の持つ、より深く、より豊かな響きの世界を発見するための、ささやかな、でも確かな一歩を踏み出すお手伝いができたなら、こんなに嬉しいことはありません。
お礼の言葉
改めまして、この長く、そして、ちょっぴり(いや、かなり?)ハードな内容だったかもしれない和声聴音の旅に、最後まで諦めずにお付き合いいただき、本当に、本当にありがとうございました!
あなたの「音楽を深く理解したい!」という素晴らしい探求心と向上心に、心からの敬意を表します。
あなたの耳が、これからたくさんの美しいハーモニーの秘密を解き明かし、あなたの音楽との絆が、さらに強く、深く、豊かなものになっていくことを、心の底から応援しています!🏳️🌈🎶
ぜひこれからも、楽しみながら、根気強く、耳を澄ませてみてくださいね! 本当にありがとうございました!😊