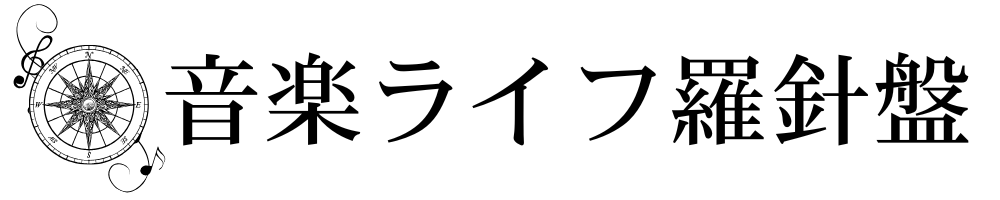はじめに:楽譜の「オタマジャクシ」、怖くない!音符がわかれば音楽は100倍楽しくなる!
突然ですが、あなたは「楽譜」、読めますか?
「うっ…見たくない…😨」 「なんか黒い丸と棒がいっぱい並んでて、暗号にしか見えない…」 「オタマジャクシの大群、見てるだけで目が回る~😵💫」
なーんて、思っていませんか?
わかります、わかりますとも!何を隠そう、この私自身が、かつては重度の楽譜アレルギー患者でしたから(笑)。音楽は大好き!でも楽譜は…できれば見たくない存在。そんな感じでした。
特に、いろんな形がある「音符(おんぷ)」!
- 「この音符とあの音符、何が違うの?」
- 「どの音符がどれくらいの長さなの?さっぱりわからん!」
- 「種類が多すぎて、全然覚えられないんだけど!😭」
- 「休符?なにそれ美味しいの?」
…こんな風に、頭の中が「???」でいっぱいになって、結局「楽譜読むの、むーりー!」って、そっと楽譜を閉じてしまう…。そんな経験、ありませんか?
でも、もし、そんなあなたの「楽譜こわい…」が、「あれ?なんだ、音符って意外と簡単じゃん!」に変わるとしたら…?
このブログ記事は、まさにそんな魔法をかけるために書かれました!🪄
この記事を最後まで読めば、あなたは…
- たくさんある「音符の種類」とその見分け方がスッキリわかる!
- それぞれの音符が持つ「長さ」が、感覚的に理解できる!
- 音符の相棒、「休符」のこともバッチリわかる!
- 楽譜を読むのが、今よりずーっと楽になる!
- 楽しくて簡単な「覚え方」のヒントも手に入る!
- そして何より、音楽を演奏したり、聴いたりするのが、今よりもっともっと楽しくなる!
「えー、ほんとにそんな上手い話あるの?」って疑っちゃいますよね? でも、大丈夫!私自身、四分音符と八分音符の区別もつかず、リズム感ゼロと言われ続けた過去があるんです…(遠い目)。でも、音符の種類と長さのルールをちゃんと理解したら、本当に世界が変わりました。楽譜を読むのが苦じゃなくなったし、音楽の聞こえ方まで変わったんです!
この記事では、難しい音楽用語はできるだけ使わずに、図をイメージしたり(実際には描けませんが!想像力でカバー!)、身近なものに例えたりしながら、楽譜入門の初心者さんにも「なるほど!」と思っていただけるように、全力でナビゲートします!💪
具体的には、こんな順番でお話ししていきますね。
- 音符ってそもそも何? まずは基本のキから!
- 基本の音符たち: よく見る主要メンバーの種類と長さを徹底解説!
- 応用編の音符たち: もう少し複雑なリズムを作る仲間たち!
- 休符も大事!: お休みのしるしの種類と長さ!
- 覚え方&読み方: 楽しくマスターするコツと実践テクニック!
さあ、構えないでくださいね!コーヒーでも片手に、リラックスして読み進めてください☕。 この記事を読み終わる頃には、きっとあなたは「オタマジャクシ」と大親友になっているはず!一緒に、音符の世界を探検しましょう!
第1章:そもそも音符って何? 楽譜の主役を知って仲良くなろう!
さあ、お待たせしました!いよいよ音符の世界へダイブ! 「楽譜って見るのもイヤ…」「オタマジャクシ怖い…」なんて思っているあなたも、大丈夫!まずは、楽譜の主役である「音符くん」の自己紹介から始めましょう!きっと仲良くなれますよ😊
楽譜って暗号?いいえ、音楽の設計図です!
まず、大前提として! 「楽譜=難しい暗号」というイメージは、今日でポイッ!っと捨てちゃいましょう!🗑️
楽譜は、作曲家が「こんな音楽だよ!」って伝えたいことを、誰にでもわかるように書き残した、**とっても便利な「音楽の設計図」や「レシピ」**みたいなものなんです。
この設計図が読めるようになれば、「どんなメロディで、どんなリズムで、どんな雰囲気の曲なのか」が、演奏する前でもわかっちゃう!すごいと思いませんか?✨
音符の役割とは?「音の高さ」と「音の長さ」を表す記号
その設計図の中で、特に重要な役割を果たしているのが、今回の主役「音符(おんぷ)」です。 この、よくオタマジャクシに例えられる記号くんは、主に2つの大事な情報を私たちに教えてくれています。
- 音の高さ (どれくらいの音?): 楽譜には横線が5本ありますよね(五線譜)。音符がその線のどの位置にあるか(線の上なのか間なのか、どの高さか)で、ドレミファソラシド…といった音の高さが決まります。(※高さについては、また別の機会に詳しく!)
- 音の長さ (どれくらいの時間?): 音符の「形」や「見た目」(●なのか○なのか、棒が付いてるか、旗🚩が付いてるかなど)によって、その音をどれくらいの時間(長さ)伸ばすのかが決まります。
今回の記事では、特にこの2つ目の役割、**「音の長さ」**に大注目していきます!ここ、めちゃくちゃ大事ですよ!
今回の主役!「音の長さ」を表す部分に注目!
なぜ「音符の長さ」がそんなに大事かって? それは、音楽のノリやグルーヴ感を作り出す、超重要な要素だからです!
例えば、同じ「ド」の音でも、 「タン・タン・タン」と短く3回鳴らすのと、 「ターーー」と長く1回鳴らすのでは、 全然印象が違いますよね?
この「タン」とか「ターー」とかいう**音の長さ(時間の使い方)**を、楽譜上で正確に示してくれるのが、音符の「形」なんです。
なぜ音符の長さを知るのが大事なの?リズムの基本だから!
そして、この音符の長さの様々な組み合わせによって生まれるのが、音楽の心臓部とも言える**「リズム」**!❤️🔥
手拍子で考えてみましょう。 「パン・パン・パン・パン」(全部同じ長さ)と、 「パン・パパン・パン・パン」(長さが違う)では、 ノリが全然違いますよね?後者の方がなんだか踊りだしたくなるような…?💃
このように、音符の長さを理解することは、音楽のリズムを正確に理解し、表現するために不可欠なんです。これがわからないと、楽譜通りに演奏したり歌ったりすることが難しくなってしまいます。
【予備知識】拍(はく)って何?音楽の時間の単位
さて、音符の長さを具体的に見ていく前に、一つだけ知っておくと便利な言葉があります。それが**「拍(はく)」**です。
「拍」って聞くと難しそうですが、全然そんなことありません!
拍 = 音楽に合わせて、私たちが自然に感じる時間の「ひと区切り」や「カウント」のこと。
- 音楽を聴きながら、ついつい手拍子👏しちゃう、あの「パン、パン、パン」という一定の間隔。
- 心臓の「ドキッ、ドキッ」という鼓動。
- 時計の「チク、タク」という秒針の動き。
これらが「拍」のイメージに近いものです。音楽が前に進んでいくための、基本的な時間の単位だと思ってください。
これから音符の種類を見ていく上で、**「この音符は、〇拍分の長さですよ~」**という風に、「拍」を基準にして説明していきます。まずは「ふーん、音楽には『拍』っていう時間の数え方があるんだな」くらいに思っておいてくださいね!
第2章:【基本のキ!】主要音符の種類と長さを完全マスター!(全音符~八分音符)
第1章では、音符が「音の高さ」と「音符の長さ」を表すこと、そして「長さ」がリズムを作る上で超重要だってこと、さらにリズムの基準となる「拍」についてお話ししましたね。
さあ、準備運動はバッチリ!ここからは、楽譜の世界で大活躍している「基本の音符ファミリー」をご紹介します!🎉
まずは、この子たちの顔(形)と名前、そして一番大事な「どれくらいの長さ(拍数)を持っているのか」をしっかり覚えていきましょう!彼らと仲良くなれれば、楽譜を読むのが一気に楽しくなりますよ!
(※ここでの音符の長さ(拍数)は、特に断りがない限り、音楽で一番よく使われる**「4/4拍子(よんぶんのよんびょうし)」**を基準に説明しますね。「4/4拍子」が何かは、今は「ふーん、そういうのが一般的なのね」くらいでOKです!)
まずはこの4人(?)を覚えよう!基本の音符ファミリー大集合!
楽譜にはいろんな種類の音符が出てきますが、まずは基本となるこの4つの音符をマスターしましょう!この4人がわかれば、大抵の曲のリズムはかなり読めるようになります!
- 全音符 (ぜんおんぷ)
- 二分音符 (にぶおんぷ)
- 四分音符 (しぶおんぷ)
- 八分音符 (はちぶおんぷ)
では、一人ずつ自己紹介してもらいましょうか!🎤
一番えらい(長い)親分!「全音符(ぜんおんぷ)」の姿と長さ
トップバッターは、音符界のボスキャラ(?)、全音符さんです!
- 見た目(形): 白い丸「○」のみ!棒も旗もなーんにも付いていない、一番シンプルな形です。
- 読み方: ぜんおんぷ
- 長さ: 4拍!! 基準となる四分音符の実に4倍の長さを持っています。 (イメージ:ターーーー)
<center>(イメージ図: ○ )</center>
この全音符が、長さの基準となる一番長い音符です。「全」という漢字からも、なんだか一番偉そうな(長そうな)感じがしますよね!まずはこの形と「4拍」という長さをセットで覚えましょう!
親分の半分!「二分音符(にぶおんぷ)」とその長さ
次にご紹介するのは、全音符の子分(?)、二分音符さん!
- 見た目(形): 白い丸「○」に、縦棒「 | 」(符幹:ふかん と言います)が生えています。
- 読み方: にぶおんぷ
- 長さ: 2拍! なんと、全音符のちょうど半分の長さなんです! (イメージ:ターー)
<center>(イメージ図: 白丸に棒がついた形 )</center>
名前の通り、「全音符」を「二つに分けた」長さを持つのが二分音符。見た目も、全音符に棒が一本加わっただけ、と覚えやすいですね!
超よく見る基本形!「四分音符(しぶおんぷ)」とその長さ
さあ、どんどん行きますよ!お次は、楽譜で一番よく見かけると言っても過言ではない、超基本形の四分音符さん!
- 見た目(形): 今度は黒い丸「●」に、縦棒「 | 」(符幹)が生えています。
- 読み方: しぶおんぷ
- 長さ: 1拍! 二分音符のさらに半分の長さ(つまり全音符の4分の1!)。これが多くの曲でリズムの基準となる長さです。 (イメージ:タン)
<center>(イメージ図: ●に棒がついた形 、いわゆる普通の音符の形 )</center>
音楽に合わせて手拍子するときの「パン!」1回分が、だいたいこの四分音符1つ分の長さと同じくらいです。形も「黒丸に棒」と、一番「音符っぽい」形ですよね!まずはこの四分音符=1拍、としっかり覚えましょう!
ちょっと忙しいぞ!「八分音符(はちぶおんぷ)」とその長さ
基本ファミリーの最後は、ちょっと動きが細かい八分音符さん!
- 見た目(形): 黒い丸「●」に、縦棒「 | 」(符幹)、さらに旗「 ♪ 」(符尾:ふび と言います)が1本付いています。 ※八分音符が2つ以上連続すると、旗の部分が線で繋がれることがあります(連桁:れんこう と言います)。見た目は変わりますが、長さは同じです!
- 読み方: はちぶおんぷ
- 長さ: 0.5拍(半拍)! 四分音符のさらに半分の長さ(全音符の8分の1!)です。 (イメージ:タ)
<center>(イメージ図: ♪ や、♪が2つ繋がった形 )</center>
四分音符よりも短いので、八分音符がたくさん出てくると、ちょっと速い、細かいリズムになります。「旗が1本付いてるやつは、四分音符の半分!」と覚えましょう。
【超重要!】音符の長さの関係が一目でわかる!ピザ分割の法則🍕(イメージ図解)
さあ、ここまで4つの基本音符を見てきましたが、ここで一番大事なポイント!それは、**それぞれの音符の「長さの関係性」**です!
これを理解するのに、とっても分かりやすい例えがあります。それは…「ピザの分割」!🍕
想像してみてください。
- まず、大きなまんまるピザが1枚あります。これが全音符(4拍)だとしましょう。 <center>(イメージ:大きな円 ○ )</center>
- このピザを、真ん中から半分にカット!✂️ すると、2枚のピザができますね。この1枚が二分音符(2拍)です。 <center>(イメージ:円が縦線で半分に割られた形 )</center>
- さらに、その半分になったピザを、もう一度半分にカット!✂️ すると、全部で4枚のピザになりますね。この1枚が四分音符(1拍)です。 <center>(イメージ:円が十字に4等分された形 )</center>
- 最後に、その4分の1サイズのピザを、さらに半分にカット!✂️ すると、全部で8枚の小さなピザになります。この1枚が八分音符(0.5拍)です! <center>(イメージ:円が8等分された形 )</center>
どうでしょう?
全音符 (4拍) = 二分音符 (2拍) × 2枚 二分音符 (2拍) = 四分音符 (1拍) × 2枚 四分音符 (1拍) = 八分音符 (0.5拍) × 2枚
という関係性が、イメージできたでしょうか? 音符の長さは、どんどん半分、半分になっていく! この関係性をしっかり頭に入れておくことが、リズムを理解する上でめちゃくちゃ重要なんです!
第3章:もっとリズムを豊かに!応用編の音符たちを仲間に入れよう!
第2章では、全音符、二分音符、四分音符、八分音符という、楽譜界のレギュラーメンバーをご紹介しましたね!ピザの例え🍕で、音符の長さの関係性もバッチリ理解できた…はず!
「これで、もう大体の楽譜は読めるんじゃない?😎」 なーんて思ったそこのあなた!ふふふ、甘い!( ̄ー ̄)ニヤリ
実は、音楽のリズムの世界はもっともっと奥深いんです!基本のファミリーだけでは表現しきれない、もっと細かい動きや、ちょっと変わったノリを作り出すために、頼もしい「応用キャラ」たちが存在します。
この章では、そんな応用編の音符たち…十六分音符、付点音符、そしてリズムを繋いだり分割したりする記号「タイ」「三連符」について解説していきます!これらをマスターすれば、あなたのリズム感はさらにレベルアップ間違いなしですよ!🚀
さらに短くテキパキと!「十六分音符(じゅうろくぶおんぷ)」登場!
まずは、八分音符よりもさらにスピーディーなこの子!
- 見た目(形): 黒い丸「●」に、縦棒「 | 」、そして旗が2本「 ♬ 」付いています! ※八分音符と同じように、2つ以上連続すると旗の部分が線で繋がれます(連桁)。旗2本なので、繋がる線も2本になります。
- 読み方: じゅうろくぶおんぷ
- 長さ: 0.25拍! なんと、八分音符のさらに半分の長さ(四分音符の4分の1!)です。 (イメージ:タッ)
<center>(イメージ図: ♬ や、♬が4つくらい線2本で繋がった形 )</center>
八分音符の旗が1本だったのに対し、十六分音符は旗が2本!これが一番の見分けるポイントです。 ピザの例えで言うと、八分音符サイズ(8等分)のピザを、さらに半分にカットした細かさ!🍕➡️🔪➡️ 極小ピザ! この音符がたくさん出てくると、かなり速くて細かい、「パラパラパラ…」といった感じのリズムになります。ロックやポップスのドラムパターンなんかでよく耳にしますね!
しっぽが生えると長さが変わる?魔法の点「付点(ふてん)音符」の秘密
お次は、音符の長さをちょっとだけ伸ばしたい時に使う、便利な魔法!「付点(ふてん)」です。
- 付点とは?: 音符のすぐ右隣に付いている、小さな点「・」のことです。
<center>(イメージ図: 音符 ● の右横に点 ・ が付いている )</center>
この「点」が付くと、音符の長さはどうなるのか? ルールは意外とシンプル!
魔法のルール:付点が付いた音符は、元の音符の長さ + 元の音符の半分の長さ になる!
…ちょっと分かりにくい?😅 具体的に見てみましょう!
代表的な付点音符とその長さ
- 付点二分音符:
- 元の二分音符の長さは「2拍」でしたね。
- その半分の長さは「1拍」です。
- なので、付点二分音符の長さは 2拍 + 1拍 = 3拍! <center>(イメージ:白丸棒付き音符の横に点)</center>
- 付点四分音符:
- 元の四分音符の長さは「1拍」。
- その半分の長さは「0.5拍」(=八分音符1つ分)。
- なので、付点四分音符の長さは 1拍 + 0.5拍 = 1.5拍! <center>(イメージ:黒丸棒付き音符の横に点)</center> (※「タータ」のような「タッカタッカ」のリズムでよく使われます)
- 付点八分音符:
- 元の八分音符の長さは「0.5拍」。
- その半分の長さは「0.25拍」(=十六分音符1つ分)。
- なので、付点八分音符の長さは 0.5拍 + 0.25拍 = 0.75拍! <center>(イメージ:♪の横に点)</center> (※付点四分音符よりもさらに細かい「タッタ」のリズムで使われます)
この付点音符は、リズムに独特の「タメ」や「跳ねる感じ」を生み出すのに欠かせない存在。「1.5拍」とか「0.75拍」とか、ちょっと中途半端な長さを作れるのがミソなんです!
音符同士を合体!「タイ」ってどんな役割?
次に紹介するのは、「タイ」と呼ばれる記号です。これは音符そのものではなく、音符同士を結びつける役割を持っています。
- 見た目: 同じ高さの2つの音符を、弧線「⌒」で結びます。
<center>(イメージ図:同じ高さの音符2つが ⌒ で繋がっている)</center>
- 役割: タイで結ばれた2つの音符は、別々の音として演奏(または歌う)のではなく、1つの音として、それぞれの長さを合計した分だけ伸ばします。音を合体させて長くする接着剤みたいなものですね!
例:
- 四分音符(1拍)と四分音符(1拍)がタイで結ばれていたら… → 1+1=2拍、つまり二分音符と同じ長さになります。
- 二分音符(2拍)と八分音符(0.5拍)がタイで結ばれていたら… → 2+0.5=2.5拍分の長さになります。
付点音符と似てるけど、ちょっと違うんです。
- 付点音符: 1つの音符に点を付けて、長さを「元の長さの1.5倍」にする。
- タイ: 2つ以上の同じ高さの音符を繋げて、長さを「合計」する。
タイは、小節線をまたいで音を伸ばしたい時や、付点音符では作れない微妙な長さを作りたい時などによく使われます。これも重要な記号なので、覚えておきましょう!
ちょっと特殊なリズム「三連符(さんれんぷ)」ってなんだ?
基本のリズムは、1拍を2つ(八分音符×2)や4つ(十六分音符×4)に分けていくのが普通でしたよね。でも、世の中には「いやいや、俺は1拍を3つに分けたいんだ!」という、ちょっと変わったリズムが存在します。それが**「三連符(さんれんぷ)」**!
- 見た目: 主に3つの音符(八分音符が多い)を連桁(れんこう:繋がっている線)でつなぎ、その上に「3」という数字が書かれていることが多いです。
<center>(イメージ図:♪が3つ繋がっていて、上に「3」と書いてある)</center>
- 考え方: 本来なら2つ入るはずの長さ(例えば1拍)のところに、**無理やり3つの音符を均等に入れる!**という特殊なリズムです。
- 例:四分音符(1拍)の長さに、八分音符を3つ均等に入れる → 「八分音符の三連符」
- リズムの感覚: 通常の「タ・タ」(八分音符2つ)のリズムに対して、三連符は「タ・タ・タ」という、少し転がるような、跳ねるような独特のノリになります。口で言うなら「タ・ケ・ヤ」(竹屋)とか、「バ・ナ・ナ」🍌みたいな感じのリズムに近いかも?
三連符はブルースやジャズ、ポップスなど、いろんなジャンルの曲で使われる、表情豊かなリズムです。最初はちょっと戸惑うかもしれませんが、「1拍を3分割するやつね!」と覚えておけばOK!
(コラム)世にも奇妙な(?)激レア音符コレクション
さて、十六分音符まで来ましたが、実は音楽の世界には、もっともっと短い音符が存在するんです!
- 三十二分音符: 十六分音符のさらに半分!旗が3本付きます!もう、楽譜が真っ黒け!
- 六十四分音符: 三十二分音符のさらに半分!旗が4本!ここまで来ると、もはや芸術の域…?
これらの音符は、クラシックの速いパッセージ(フレーズ)などで稀に見かけることがありますが、ポップスなどではあまりお目にかかれません。
他にも、昔の楽譜(中世とかルネサンス時代とか)には、現代とは違う形や意味を持つ音符がたくさん使われていました。ひし形◇の音符とか、もっと複雑な記号とか…。興味があったら調べてみると、音符の歴史の奥深さに触れられて面白いかもしれませんよ!
音符の世界、意外とバラエティ豊かで、知れば知るほど面白いんです!
第4章:「お休み」も大事!休符の種類と長さを覚えよう
さて、ここまで「音を出す長さ」を指定する音符について学んできましたね。 でも、音楽って、ずーっと音が鳴りっぱなしなわけじゃありません。時には「シーン…」とした静寂、つまり「音を出さない時間」がありますよね?
この**「音を出さない時間(お休みする時間)」の長さを、楽譜上で示してくれるのが「休符(きゅうふ)」**なんです!
「えー、お休みなら別に書かなくてもいいんじゃない?」って思うかもしれませんが、とんでもない!この「お休み」=休符も、音楽のリズムを作り、曲にメリハリや表情を与えるための、めちゃくちゃ大事な要素なんですよ!
この章では、音符の頼れる相棒、休符の種類と長さ、そして覚え方のコツをマスターしましょう!
音を出さない時間も音楽の一部!「休符(きゅうふ)」の役割
レストランで、美味しい料理の合間にちょっとお水やお茶を飲むと、次の料理がもっと美味しく感じられたりしますよね?🍹
音楽における休符も、それにちょっと似ています。 音と音の間に適切なお休み(休符)が入ることで、
- リズムにメリハリが生まれる!
- フレーズの区切りが分かりやすくなる!
- 音楽に「呼吸感」や「間(ま)」が生まれて、表情豊かになる!
…といった効果があるんです。ただの「無音」じゃない、積極的な意味を持つ「お休み」、それが休符なんですね。
音符とセットで覚えよう!主な休符の種類と長さ
朗報です!休符の種類と長さは、これまで学んできた音符と完全にペアになっています! つまり、全音符に対応する「全休符」、二分音符に対応する「二分休符」…というように、同じ名前の音符と同じ長さだけお休みする、と考えればOK!これは覚えやすい!👍
では、主な休符の顔(形)と名前、長さを見ていきましょう!
- 全休符 (ぜんきゅうふ)
- 対応する音符: 全音符
- 長さ: 4拍 お休み
- 形: 五線譜の上から2番目の線(第4線)から下にぶら下がっている太い長方形のブロック。 <center>(イメージ:線の【下】にくっついた黒い長方形)</center>
- 二分休符 (にぶきゅうふ)
- 対応する音符: 二分音符
- 長さ: 2拍 お休み
- 形: 五線譜の真ん中の線(第3線)の上に乗っかっている太い長方形のブロック。 <center>(イメージ:線の【上】にくっついた黒い長方形)</center>
- 四分休符 (しぶきゅうふ)
- 対応する音符: 四分音符
- 長さ: 1拍 お休み
- 形: ニョロっとした独特の形。よく「うなぎ」とか「カミナリ」「Z」みたい、と例えられます(笑)。書き順もちょっと練習が必要かも?
- <center>(イメージ:例のニョロっとした形)</center>
- 八分休符 (はちぶきゅうふ)
- 対応する音符: 八分音符
- 長さ: 0.5拍(半拍) お休み
- 形: 左上から右下に斜めの線が伸び、その先端に点(ひげ)が1つ付いている形。「 Y 」や数字の「7」に似てる?
- <center>(イメージ:「 Y 」の棒の右下に点が付いたような形)</center>
- 十六分休符 (じゅうろくぶきゅうふ)
- 対応する音符: 十六分音符
- 長さ: 0.25拍 お休み
- 形: 八分休符の点(ひげ)が2つになった形。
- <center>(イメージ:八分休符の点の下にもう一つ点が付いたような形)</center>
まずは、これらの休符の形と、対応する音符と同じ長さだけ休む、ということをしっかり覚えましょう!
見た目が似てる?全休符と二分休符の見分け方
初心者さんが一番「どっちだっけ!?」と混乱しやすいのが、形がそっくりな全休符と二分休符。どちらも長方形のブロックですが、五線譜の線の上にあるか下にあるかが違います。
これには、有名な覚え方があります!
- 覚え方①:重さで覚える!
- 「全休符(4拍休み)は長くて重いから、線からぶら下がってる(下)!」
- 「二分休符(2拍休み)は軽いから、線の上に乗っかってる(上)!」
- 覚え方②:形で覚える!
- 「全休符は、(天井から吊るされた)シルクハット🎩みたい!(線の下)」
- 「二分休符は、(テーブルの上の)お皿🍽️みたい!(線の上)」
どうでしょう?どちらか覚えやすい方で、この二つの違いをしっかりマスターしてくださいね!ここを間違えると、リズムが大変なことになっちゃいますから!😂
付点休符もあるの?基本的な考え方
音符に「付点」が付いて長さが元の1.5倍になったように、実は休符にも「付点」が付くことがあるんです!
- 見た目: 休符のすぐ右隣に、小さな点「・」が付きます。
<center>(イメージ図: 四分休符 𝄽 の右横に点 ・ が付いている )</center>
考え方は付点音符と全く同じ!
魔法のルール再び:付点が付いた休符は、元の休符の長さ + 元の休符の半分の長さ だけ休む! (つまり、元の休符の長さの1.5倍お休みする、ということです!)
例:
- 付点四分休符:
- 元の四分休符の長さは「1拍」休み。
- その半分の長さは「0.5拍」休み。
- なので、付点四分休符の長さは 1拍 + 0.5拍 = 1.5拍 お休み!
- 付点八分休符:
- 元の八分休符の長さは「0.5拍」休み。
- その半分の長さは「0.25拍」休み。
- なので、付点八分休符の長さは 0.5拍 + 0.25拍 = 0.75拍 お休み!
付点休符も、リズムに独特のニュアンスを与えるために使われます。付点音符ほど頻繁には出てこないかもしれませんが、「休符にも点が付くことがあって、ルールは音符と同じ!」と覚えておけば大丈夫ですよ!
【確認クイズ】この音符/休符の長さは?
さあ、ここまで音符と休符の基本的な長さについて学んできましたね! ちょっと頭の体操!ここで簡単なクイズです!下の記号はそれぞれ何拍分の長さ(またはお休み)になるでしょうか?(4/4拍子の場合で考えてみてね!)
- ♩ (四分音符) = ? 拍
- ♪ (八分音符) = ? 拍
- 𝄽 (四分休符) = ? 拍
- 𝄾 (十六分休符)= ? 拍
- ♩. (付点四分音符)= ? 拍
- 𝄼. (付点八分休符)= ? 拍
- ○ (全音符) = ? 拍
- (白丸棒付き休符) (二分休符) = ? 拍
(答えは下にスクロール!) ↓ ↓ ↓ 【答え】
- 1拍
- 0.5拍
- 1拍 休み
- 0.25拍 休み
- 1.5拍
- 0.75拍 休み
- 4拍
- 2拍 休み
どうでしたか? 全問正解できたあなたは、もう音符と休符の長さの基本はバッチリかも!🎉 間違えちゃった方も、全然気にしないでくださいね!繰り返し見ていくうちに、必ず覚わりますから😊
第5章:これであなたも音符マスター!楽々覚え方&読み方実践テクニック
ここまで本当にお疲れ様でした! 第2章から第4章にかけて、基本的な音符から応用編の音符、そして相棒の休符まで、たくさんの種類と長さを学んできましたね。
「よし、これで音符の種類と長さは理解したぞ!」 「でも…正直、全部覚えるのが大変そう…💦」 「実際に楽譜を見たときに、スラスラ読めるようになるのかなぁ…?」
ふふふ、その気持ち、よーくわかります!知識をインプットするのと、それを実際に「使える」ようになるのとは、また別問題ですもんね。
でも、ご安心ください!この最終章では、あなたが覚えた音符や休符の知識をしっかりと定着させ、楽譜を読むときにスムーズに活かせるようになるための、とっておきの「覚え方」&「読み方」実践テクニックを伝授しちゃいます!これで楽譜への苦手意識ともサヨナラ!👋
リズム打ちで体感!音符の長さを身体で覚える方法👏🦶
まず、音符の長さ、つまりリズムを覚える上で一番効果的なのは、頭だけでなく「身体」で覚えること!
机に向かって教科書を眺めているだけじゃ、なかなかリズム感は身につきません。実際に身体を動かして、音符の長さを体感してみましょう!
【リズム打ちトレーニングの基本】
- メトロノームを用意: スマホのアプリなどでOK!まずはゆっくりめのテンポ(例:♩=60くらい)に設定します。
- 基本の拍を打つ: メトロノームの「カチッ」という音(これが四分音符=1拍の目安)に合わせて、手拍子👏や足踏み🦶で正確に拍を打ちます。これが全ての基本!
- 音符の長さで打ち分ける:
- 四分音符 (♩) → 1拍に1回「パン!」と打つ。
- 八分音符 (♪) → 1拍に2回「パパン!」と均等に打つ。(1拍を2等分する感じ)
- 十六分音符 (♬) → 1拍に4回「パパパパッ!」と均等に打つ。(1拍を4等分!)
- 二分音符 (白丸棒付き) → 「パーン(伸ばす)」と2拍分打ち続ける(または1拍目で打ち、2拍目まで心で数える)。
- 全音符 (○) → 「パーーーーン(伸ばす)」と4拍分打ち続ける(または心で数える)。
- 休符 → 対応する音符と同じ拍数分、音を出さずに心で数える(「ウン」と言うのもアリ)。
最初はゆっくり、確実に!慣れてきたら少しずつテンポを上げてみましょう。 簡単なリズムパターン(例:「♩ ♪ ♪ ♩」など)を楽譜で見ながらリズム打ちする練習も効果的です。 身体がリズムを覚えてくると、楽譜を見ただけで自然と長さがイメージできるようになりますよ!
声に出して読む!リズム読み(リズム唱)のススメ🗣️
身体で覚えるのと同時に、声に出してリズムを読む練習も、とってもおすすめです!これを**「リズム読み」や「リズム唱」**と言います。
これは、楽譜に書かれている音符や休符のリズムを、特定の音の高さではなく、一定の読み方で声に出して読む練習です。
【リズム読みの例】
- 四分音符 (♩) → 「タン」
- 八分音符 (♪) → 「タ」(または、♪♪で「タタ」)
- 十六分音符 (♬) → 「テ」(または、♬♬♬♬で「テケテケ」)
- 二分音符 (白丸棒付き) → 「ター」(または「ターン」)
- 全音符 (○) → 「ターー」(または「ターアン」)
- 休符 → 「ウン」(または「ン」)
例えば、こんなリズムがあったら… 「 ♩ ♪ ♪ | ♩. ♪ | ♬♬♬♬ 𝄽 」
これをリズム読みすると… 「タン・タ・タ | ター・タ | テケテケテケ・ウン」 という感じになります。(※読み方は自由ですが、一貫性を持たせると良いです)
メトロノームに合わせて声に出して読むことで、リズムの流れをより明確に捉えることができますし、頭の中だけで考えるよりもずっと楽譜を読むスピードが上がります!最初はゆっくり、慣れたら少しずつ速く読んでみましょう!歌うように楽しくやるのがコツですよ♪
覚え方のコツ①:音符の「見た目」と長さを関連付ける!(旗の数など)👀🔗
たくさんの音符や休符の形と長さ、覚えるのが大変…という方は、「見た目の特徴」と「長さ」を結びつけて覚えるのがおすすめです!
- 旗(符尾)の数で覚える!
- 八分音符 (♪) → 旗が1本 → 四分音符の半分
- 十六分音符 (♬) → 旗が2本 → 八分音符の半分(さらに短い!)
- 三十二分音符 (旗3本!) → 十六分音符の半分(もっと短い!) → **旗が増えるほど、音符の長さは半分になっていく!**と覚えましょう!
- 白黒で覚える!
- 白い音符 (○ 全音符, 白丸棒付き 二分音符) → 長さが長い(2拍以上)
- 黒い音符 (♩ 四分音符, ♪ 八分音符, ♬ 十六分音符…) → 長さが短い(1拍以下) → 大雑把ですが、これだけでも見分けるヒントになります!
- 休符の見分け方(復習)
- 全休符 → 線の下にぶら下がる(重い帽子🎩)
- 二分休符 → 線の上に乗っかる(軽いお皿🍽️)
- 八分休符 → 点(ひげ)が1つ
- 十六分休符 → 点(ひげ)が2つ → 休符も見た目の特徴で覚えましょう!
覚え方のコツ②:身近な言葉でリズムパターン化!(例:リンゴ、バナナ)🗣️➡️🎵
よく使われるリズムのパターンを、身近な言葉や食べ物の名前に置き換えて覚えるのも、楽しくて効果的な方法です!特に、子供に教えるときにも使えますよ。
【リズム言葉の例】(1拍を基準に)
- ♩ (タン) → 「パン」「ドン」「1(いち)」
- ♪ ♪ (タタ) → 「りんご」🍎「ぶどう」🍇「2こ(にこ)」
- ♬ ♬ ♬ ♬ (テケテケ) →「チョコレート」🍫「パイナップル」🍍「4こ(よんこ)」
- ♩. ♪ (タータ) → 「カレー」🍛「シュークリーム」「3・つ(みっ・つ)」
- ♪ ♩ ♪ (タ・タン・タ) → 「ポテ・トー」🍟「すい・かー」🍉
これはあくまで一例なので、自分が言いやすくて、リズムに合う言葉を自由に作ってみるのも面白いですよ! 言葉のリズムと音符のリズムを結びつけることで、自然と口ずさめるようになり、記憶に定着しやすくなります。
覚え方のコツ③:音符カードやアプリでゲーム感覚学習!🃏📱
やっぱり、楽しく覚えるのが一番! ゲーム感覚で音符や休符を覚えられるツールを活用しない手はありません!
- 音符カード:
- 市販されている音符カード(表に音符の形、裏に名前や長さが書いてある)を使うのも良いですし、自分で厚紙などに書いて手作りするのもおすすめです。
- カルタのように読み札を読んで取るゲームや、神経衰弱のように同じ長さの音符と休符を当てるゲームなど、遊び方は無限大!家族や友達とやると盛り上がりますよ!
- 学習アプリ:
- 第3章・第4章でも少し触れましたが、スマホやタブレットのアプリには、音符の種類や長さ、リズムパターンなどをクイズ形式で楽しく学べるものがたくさんあります。
- スキマ時間に手軽に取り組めますし、正解するとポイントが貯まったり、レベルアップしたりする機能があると、モチベーション維持にも繋がりますよね!
「勉強」と思うと気が重いかもしれませんが、「ゲーム」だと思えば、ついつい夢中になってしまうかも?自分に合った楽しい学習法を見つけてみてくださいね!
【実践】簡単な楽譜で、音符の長さを意識してみよう!
さあ、知識とテクニックをインプットしたら、最後はやっぱり実践です!
まずは、童謡や簡単な練習曲など、できるだけシンプルな楽譜を用意しましょう。そして、
- 音符と休符をチェック: 出てくる音符と休符の種類を一つずつ確認し、それぞれが何拍分の長さなのかを書き込んでみる。
- リズム読み: メトロノームに合わせて、声に出して「タン・タタ・ウン…」とリズム読みをしてみる。
- リズム打ち: リズム読みができるようになったら、手拍子でリズム打ちをしてみる。
- (可能なら)演奏/歌唱: 楽器で弾いてみたり、歌ってみたりする。この時も、音符と休符の長さをしっかり意識して!
最初は、音の高さは無視して、リズムだけに集中するのも良い方法です。 焦らず、一歩一歩、簡単な楽譜からでOK!楽譜を読む経験を積み重ねていくことが、音符マスターへの一番の近道ですよ!
まとめ:音符の種類と長さがわかれば、楽譜はもう怖くない!音楽の世界へ飛び込もう!
いやー!音符と休符たちの世界、探検お疲れ様でした! もしかしたら、頭の中がオタマジャクシでいっぱいになっているかもしれませんね(笑)。 ここまで長い道のりにお付き合いいただき、本当に、本当にありがとうございます!!😭🙏
この記事を読む前は、「音符の種類なんてチンプンカンプン…」「長さとか言われても…」「楽譜なんて読めなーい!」と思っていたかもしれません。
でも、どうでしょう? 全音符親分から、十六分音符くん、そして相棒の休符さんたちまで、いろんなキャラクター(?)と出会って、少しは「なんだ、意外と面白いやつらじゃん!」「これなら友達になれるかも!」って、思っていただけたなら、めちゃくちゃ嬉しいです!✨
最後に、この冒険で手に入れた「音符マスターへの道しるべ」を、ぎゅぎゅっとまとめておきましょう!
【音符&休符マスターへの道しるべ】
- 音符の基本: 音符は「音の高さ」と「音の長さ」を表す記号!長さがリズムを作る!(第1章)
- 基本ファミリー: 全音符(4拍)、二分音符(2拍)、四分音符(1拍)、八分音符(0.5拍)!長さの関係はピザで覚えよう!🍕(第2章)
- 応用キャラ: 十六分音符(0.25拍)、付点音符(元の1.5倍)、タイ(合体!)、三連符(3分割!)でリズムはもっと豊かに!(第3章)
- 休符も忘れずに: 音符と同じ長さだけお休み!全休符と二分休符の見分け方もマスター!(第4章)
- 覚え方の秘訣: 体で覚えるリズム打ち!声に出すリズム読み!見た目・言葉・ツール活用で楽しく覚えよう!(第5章)
そう、音符と休符は、音楽という言葉を書き記すための**「基本の文字」のようなもの。 ひらがなやアルファベットを覚えれば、本を読んだり文章を書いたりできるようになるのと同じように、音符と休符**を理解すれば、楽譜という音楽の設計図を読み解き、音楽の世界をもっと深く、もっと自由に楽しむことができるようになるんです!
最初は難しく感じるかもしれません。でも、焦らなくて大丈夫!
さあ、覚えた知識を武器に、楽譜の世界へ一歩踏み出してみませんか? もう、あなたは楽譜入門の入り口に立っています!
- まずは、知っている曲の簡単な楽譜を開いて、音符の長さを数えてみる?
- スマホのメトロノームアプリに合わせて、四分音符のリズム打ちを5分だけやってみる?
- この記事で紹介した「覚え方のコツ」、どれか一つ試してみる?
どんなに小さな「やってみた!」でも、それがあなたの音楽人生を変える、大きな一歩になるかもしれません。 「できた!」という小さな成功体験が、やがて大きな自信へと繋がっていきますよ!
私も昔は本当に楽譜が苦手だったので、皆さんの気持ち、本当によくわかります。でも、音符がわかるようになった時の、あの「世界がパーッと開ける感覚」は、格別です!音楽を聴くのも、演奏する(フリをするのも笑)のも、何倍も楽しくなりました。
この記事が、あなたが楽譜と、そして音楽ともっと仲良くなるための、小さなきっかけになれたら最高に嬉しいです!
お礼の言葉
改めまして、このとっても長くて、ちょっとテンション高めな(笑)記事を、最後まで、本当に最後までお読みいただき、ありがとうございました!
あなたの貴重な時間を、音符と休符たちとの時間に費やしてくださったこと、心から感謝しています。
音符が読めるようになることで、あなたの音楽ライフが、これまで以上にキラキラ輝き、楽しくて豊かなものになることを、心の底から応援しています!🏳️🌈🎶
ぜひ、いろんな楽譜にチャレンジして、音楽の世界を思いっきり楽しんでくださいね! 本当にありがとうございました!😊