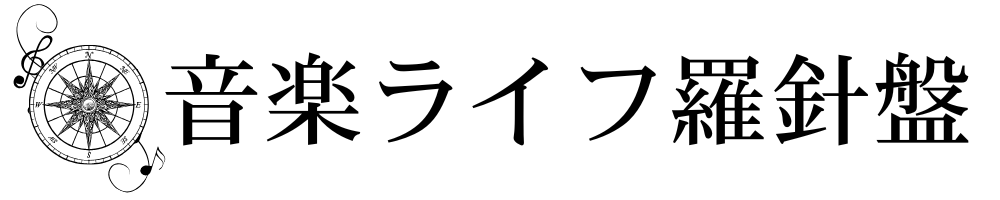はじめに:「あの人、絶対音感持ってるんだって!」憧れの(?)能力の正体とは?
「〇〇さんって、絶対音感があるらしいよ!」 「小さい頃からピアノやってたから、絶対音感が身についたんだって!」
音楽をやっている人なら、あるいは音楽好きなら、一度はこんな会話を耳にしたことがあるのではないでしょうか?
なんだか、特別な才能、選ばれし者の能力…みたいな、ちょっと憧れの対象として語られることも多い「絶対音感」。
でも、
- 「絶対音感って、具体的にどんな能力なの?」
- 「テレビで見る『天才キッズ』だけのものじゃないの?」
- 「相対音感っていうのも聞くけど、絶対音感と何が違うの?」
- 「持っていると、やっぱり音楽に有利なの?(メリットは?)」
- 「逆に、困ること(デメリット)もあるって本当?」
- 「自分にもあるのかな?チェックしてみたい!」
- 「今からトレーニングして身につけられるものなの…?」
などなど、たくさんの「?」が頭に浮かんでいる方も多いはず。 絶対音感って、なんだかベールに包まれた、ミステリアスな存在ですよね!🤔
この記事は、そんな「絶対音感」の謎を解き明かすために書かれました!
この記事を最後まで読めば、あなたは…
- 憧れの(?)「絶対音感とは何か?」その正体と仕組みがスッキリわかる!
- 絶対音感と、もう一つの大事な音感「相対音感」との明確な違いが理解できる!
- 持っていると有利?不利?絶対音感のリアルなメリットとデメリットがわかる!
- 大人でも絶対音感は身につく?気になるトレーニングの可能性について知れる!
- 自分にもあるかも?簡単なチェック方法(目安)もご紹介!
- 絶対音感に対する正しい知識が身につき、音楽の聴き方や学び方が変わるかも!
何を隠そう、この私自身は、残念ながら(?)絶対音感を持っていません!😅 昔は「絶対音感さえあれば、音楽人生バラ色なのに!」なんて本気で思っていた時期もありました(笑)。
でも、音楽について学んだり、たくさんの音楽家の方々と接したりする中で、絶対音感が全てではないこと、そしてもう一つの音感である「相対音感」がいかに重要で、トレーニングで伸ばせる素晴らしい能力であるかを知り、音感に対する考え方がガラッと変わったんです。
だから、この記事は、絶対音感を持っている方はもちろん、持っていない方にも、きっと新しい発見や気づきがあるはず!
噂やイメージに惑わされず、絶対音感の「真実」に一緒に迫っていきましょう!この記事では、
- 絶対音感の基本(定義・仕組み)
- 相対音感との違い
- メリット・デメリット
- トレーニングの可能性
- 簡易チェック方法
という順番で、絶対音感の謎を一つ一つ解き明かしていきます。難しい専門用語はなるべく避け、分かりやすく解説していきますので、リラックスしてお付き合いくださいね!
さあ、あなたも絶対音感のミステリーツアーへ、出発進行!🚀
第1章:そもそも「絶対音感」ってどんな能力?その仕組みを説明!
さて、「はじめに」で絶対音感への興味や疑問に触れましたが、いよいよその正体に迫っていきましょう!この章では、まず「絶対音感とは、そもそもどんな能力なのか?」その定義と、ちょっぴり不思議な仕組みについて、やさしく説明していきますよ!
「絶対音感」の定義:音を聴いただけで、その音名(ドレミ)がわかる能力
まず、絶対音感の定義をハッキリさせておきましょう!
絶対音感とは… 特定の音を聴いたときに、他の音と比較することなく、その音の「絶対的な高さ(周波数)」を、固有の「音名(ドレミファソラシドや、CDEなど)」として、瞬時に認識できる能力
のことです!
…って、ちょっと硬い説明ですね😅
もっと簡単に言うと、
- ピアノの鍵盤を見ずに「ポーン!」と鳴らされた音が、「あ、今の『ファ♯』だ!」と瞬時にわかる。
- 曲を聴いていて、そのメロディが「ソ・ミ・ミ~♪ ファ・レ・レ~♪」と、具体的な音名で頭の中で聴こえてくる。
- 日常生活の音(救急車のサイレン🚑、踏切の音、電子レンジの「チン!」という音など)も、「あ、今の音は『シ♭』くらいかな?」みたいに、音名として感じられる。
こんな能力を持っている人が、「絶対音感がある」と言われます。まるで、色を見た瞬間に「これは赤!」「これは青!」とわかるように、音を聞いた瞬間に「これはド!」「これはソ!」とわかる、そんな感覚に近いのかもしれませんね🎨🎶。
どれくらいレアなの?持っている人の割合は?
「へぇー!やっぱりすごい能力なんだ!」 「じゃあ、絶対音感を持ってる人って、どれくらいいるの?」
気になりますよね? 実は、絶対音感を持っている人の正確な割合を調べるのは難しいのですが、一般的にはかなり珍しい能力だと考えられています。
研究によって数字は異なりますが、
- 数百人~数千人に一人
- 音楽を専門的に学んでいる人の中でも、数パーセント程度
などと言われることが多いようです。(もちろん、後天的なトレーニングによる影響なども考慮する必要がありますが)
いずれにしても、誰もが持っている能力というわけではなく、比較的希少な能力であることは間違いなさそうですね…!
どうやって音を認識してるの?~脳科学的な視点も少しだけ~
「でも、なんで絶対音感がある人は、音を聞いただけでドレミがわかるの?」 その仕組み、不思議ですよね?
実は、この絶対音感の仕組みについては、まだ完全に解明されているわけではありませんが、近年の脳科学の研究などから、いくつか有力な説が出てきています。
- 脳の特定の領域の働き: 絶対音感を持つ人は、音を処理する際に、左脳の特定の領域(言語処理に関わる部分に近い場所)が、持たない人に比べて活発に働く傾向がある、という研究結果があります。音を単なる「音」としてだけでなく、「音名」という言語的な情報と結びつけて処理している可能性が考えられています。
- 臨界期(感受性期)の影響: 人間の脳には、特定の能力を獲得しやすい「臨界期(りんかいき)」または「感受性期(かんじゅせいき)」と呼ばれる時期があると考えられています。絶対音感に関しても、一般的に幼児期(特に6歳くらいまで)に、音の高さ(周波数)と音名を結びつける適切な音楽体験(トレーニング)を受けることが、習得に非常に重要だとされています。この時期を過ぎると、新たに絶対音感を身につけるのは難しくなると言われています。
…と、少し専門的な話になりましたが、要するに、幼い頃の脳の特別な働きと、その時期の音楽環境が、絶対音感の獲得に大きく関わっているらしい、ということですね!脳のミステリー!🧠✨
絶対音感にもレベルがある?「なんとなくわかる」から「完璧」まで
ここで一つ注意しておきたいのが、「絶対音感」と一口に言っても、実はその能力のレベルや精度には、人によって大きな個人差があるということです。
- ピアノの音は完璧にわかるけど、他の楽器の音や人の声、生活音になると、ちょっと怪しい…
- 特定の音域(例えば真ん中くらいの高さ)は得意だけど、すごく高い音や低い音は苦手…
- 音を聞いた瞬間にパッとわかる人もいれば、少し考えてから「たぶん〇〇の音かな?」とわかる人もいる…
- 白鍵の音(ドレミファソラシ)はわかるけど、黒鍵の音(♯や♭)の判別は苦手…
などなど、「絶対音感=すべての音が100%完璧に、瞬時にわかる」というわけではないんですね。グラデーションがある、と考えた方がよさそうです。
【コラム】絶対音感を持つ(と言われる)有名人エピソード(真偽はともかく…?)
絶対音感を持つとされる有名人のエピソードは、昔から色々と語られていますよね。ちょっとだけご紹介!(※あくまで逸話として、楽しんでくださいね!)
- モーツァルト: 幼い頃、一度聴いた曲を間違いなく記憶し、演奏できたとか、遠くで鳴った教会の鐘の音の高さを正確に言い当てたとか…(天才すぎ…!)
- 現代のミュージシャン: 「曲作りで、頭の中で鳴っている音をそのまま楽譜に書き起こせるから便利」とか、「レコーディングで、ちょっとしたピッチのズレもすぐにわかる」といった話も聞かれます。一方で、「生活音が全部ドレミで聴こえてきて、逆に疲れる…」なんていう、デメリット(?)を語る方もいるようです。
これらのエピソードは、絶対音感という能力の凄さや面白さを伝えてくれますが、中には脚色された話もあるかもしれません。あくまで「へぇ~、そんな話もあるんだ」くらいに留めておくのが良いでしょう😉
これで「絶対音感とは何か?」の基本的な部分は掴めましたね! でも、音楽に必要な音感はこれだけじゃないんです!次章では、絶対音感とよく比較される、もう一つの重要な音感『相対音感』との違いを見ていきましょう!
第2章:似ているようで全く違う!「相対音感」との決定的な違いは?
第1章では、「絶対音感とは、音を聴いただけでドレミがわかる能力」であり、比較的珍しい能力だということを学びましたね。
「やっぱり絶対音感ってすごいんだなぁ…」 「音楽やるなら、絶対音感がないとダメなのかなぁ…」
なんて、思っていませんか? いやいや、ちょっと待ってください!✋
音楽の世界で活躍するために、そして音楽を深く楽しむために、実は絶対音感と同じくらい、いや、場面によってはそれ以上に重要だと言われている、もう一つの音感があるんです! それが**「相対音感(そうたいおんかん)」**です!
この章では、まず「相対音感」とはどんな能力なのかを説明し、そして「絶対音感」とは何がどう違うのか、それぞれの特徴や役割を比較しながら、その関係性を解き明かしていきましょう!
もう一つの重要な音感:「相対音感」とは?~音と音の関係性を捉える力~
では、**「相対音感」**とは、一体どんな能力なのでしょうか?
相対音感とは… ある音(基準となる音)を元にして、他の音との「相対的な高さの関係(=音程)」を正確に認識する能力
のことです!
…またちょっと硬い説明ですね😅
絶対音感が、音の高さを「絶対的な座標(住所)」で捉えるのに対し、相対音感は、音の高さを**「基準点からの距離」**で捉える、とイメージすると分かりやすいかもしれません。
【相対音感の働き方の例】
- 最初に「ド」の音がポーンと鳴ったとします。(これが基準音になります)
- 次に「ミ」の音が鳴ったとします。
- 相対音感がある人は、「あ、今の音は、さっきの『ド』の音から長3度上の音だな」というように、**2つの音の間の「距離(音程)」**を感じ取ることができます。
- さらに「ソ」の音が鳴れば、「『ド』から完全5度上の音だな」と認識できます。
このように、基準となる音さえわかれば、そこからの音程関係を頼りに、メロディの音の動きや、和音の響きを正確に捉えることができる。これが相対音感の力なんです!
(※以前の記事で紹介した「移動ド」の考え方は、まさにこの相対音感を活かしたものです!)
絶対音感 vs 相対音感:それぞれの能力を比較
では、絶対音感と相対音感、具体的に何がどう違うのでしょうか?それぞれの特徴を表で比較してみましょう!
| 特徴項目 | 絶対音感 | 相対音感 |
|---|---|---|
| 音の捉え方 | 音の絶対的な高さ(周波数)を直接認識 | **基準音からの相対的な距離(音程)**で認識 |
| 基準音の必要性 | 不要 | 必要 |
| 主な習得時期 | 幼児期の臨界期が重要とされる | 年齢に関わらずトレーニングで向上可能! |
| 移調(キーを変えること) | 苦手な場合がある(固定ド思考になりやすい) | 得意!(音の関係性は変わらないため) |
| *音楽活動での主な役割 | 音名の特定、精密なチューニングなど | メロディの把握、和音の理解、移調、合奏など |
【ポイント】
- 絶対音感: 音の高さを「点の情報」として記憶・認識するイメージ。個々の音の特定は得意だけど、音同士の関係性を捉えるのは、実は相対音感ほど得意ではない場合も。
- 相対音感: 音の高さを「線(音同士の関係性)」として認識するイメージ。基準さえあれば、どんなキーの曲でもメロディやハーモニーの関係性を理解できる。
どちらの能力も素晴らしいものですが、音の捉え方や得意なことが、全く違うんですね!
「どっちが優れている」という話ではない!それぞれの価値
ここでよくあるのが、「絶対音感と相対音感、どっちが音楽家として優れているの?」という疑問です。
結論から言うと、「どちらが優れている」という単純な話ではありません!
絶対音感も相対音感も、それぞれに素晴らしい価値があり、音楽活動において異なる役割を果たしています。
- 絶対音感は、音の絶対的な高さを正確に知りたい場面(楽器のチューニング、無調音楽の分析、絶対的な音高での採譜など)で非常に役立ちます。
- 相対音感は、曲のキーに合わせてメロディを歌ったり(視唱)、和音の響きや機能を感じ取ったり(聴音)、他の楽器とアンサンブルしたり、移調したり…といった、音楽の「関係性」の中で音を捉える必要がある、あらゆる場面で不可欠な能力です。
理想を言えば、両方の音感をバランス良く持っているのが最強かもしれませんが、それはなかなか難しいこと。大切なのは、それぞれの音感の特性を理解し、自分の持っている(あるいは鍛えたい)音感を活かしていくことです。
多くの音楽家が頼りにしているのは、実は「相対音感」?
そして、ここで重要な事実をお伝えします。 絶対音感は持っていなくても、ほとんどすべての音楽家(プロの演奏家、作曲家、歌手など)は、高度に発達した「相対音感」を持っています。 そして、日々の音楽活動の多くは、この相対音感を頼りに行われています。
なぜなら、音楽というのは、多くの場合、単独の音が鳴っているのではなく、音と音との「関係性」(メロディの流れ、和音の響き、コード進行など)の中で成り立っているからです。その「関係性」を正確に捉える相対音感こそが、音楽を深く理解し、表現するための鍵となるのです。
音楽教育の現場(特にソルフェージュ)で、音程の聴き分けや移動ドでの視唱といったトレーニングが重視されるのは、まさにこの**「相対音感」を鍛えることが、音楽能力全体の向上に不可欠**だと考えられているからです。
絶対音感は特別な才能かもしれないけれど、相対音感はトレーニングで誰でも伸ばせる、音楽を楽しむための強力な武器なんです! 次章では、そんな絶対音感が持つ「光と影」、つまりメリットとデメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう!
第3章:絶対音感の光と影?知っておきたいメリットとデメリット(注意点)
さて、絶対音感と相対音感の違いがクリアになったところで、この章では、多くの人が気になるであろう、絶対音感が持つ「光と影」…つまり、その素晴らしいメリットと、意外と知られていないかもしれないデメリット(あるいは注意点)について、詳しく見ていきましょう!これを読めば、絶対音感への見方がまた少し変わるかもしれませんよ😉
【光】絶対音感を持っていると、こんないいことが!すごいメリット!
まずは、誰もが憧れる(かもしれない)、「光」の部分から!絶対音感を持っていると、音楽活動において、こんな素晴らしいメリットがあると言われています。
メリット①:耳コピが超絶楽になる!?(音名を特定できる)🎧➡️譜面
これは絶対音感の最大のメリットの一つかもしれませんね! 聴こえてきた音楽のメロディや和音の音名を、聴いた瞬間に「ドレミ…」で特定できるので、耳コピ(耳で聴いて楽譜に書き起こしたり、演奏したりすること)が、相対音感だけの人に比べて、圧倒的に速く、正確にできる可能性があります! まるで、頭の中にリアルタイムで楽譜が表示されるような感覚!?これは確かにうらやましい…!
メリット②:調律(チューニング)のズレにすぐ気づける👂🔧
絶対音感を持つ人は、音の絶対的な高さに非常に敏感です。そのため、
- 楽器のピッチ(音の高さ)がほんの少しズレている(チューニングが狂っている)
- CDやレコードの再生速度が微妙に変わって、全体のキーが半音ズレている
といった、ごくわずかな音の高さの違いにも、すぐに気づくことができます。楽器の調律を正確に行ったり、常に正しい音程で演奏したりする上で、非常に有利な能力と言えるでしょう。
メリット③:移調奏や無調音楽への対応力が高い場合も?🎶➡️❓
- 移調奏(いちょうそう): 楽譜を異なるキーで演奏すること。絶対的な音名を把握しているので、頭の中で変換する作業が得意な場合があります。(ただし、後述するデメリットと表裏一体な面も)
- 無調音楽(むちょうおんがく): 特定のキー(調性)を持たない、複雑な現代音楽など。調性感に頼らず、一つ一つの音の絶対的な高さを捉える絶対音感は、このような音楽を理解したり演奏したりする際に役立つことがあります。
メリット④:記憶力が良い傾向も?(諸説あり)🧠
音と名前(音名)を強く結びつけて記憶する能力が、他の分野の記憶力(例えば、言語学習など)にも良い影響を与えるのではないか?という説もあります。が、これはまだ科学的に完全に証明されているわけではなく、**「そういう傾向がある人もいるかもね」**くらいに考えておくのが良いでしょう。
でも、意外なデメリット(困ること)もあるって本当?
さて、ここまで聞くと「やっぱり絶対音感、最高じゃん!」と思いますよね? でも、物事には必ず表と裏があるもの…。絶対音感を持つことで、逆に困ってしまったり、苦労したりする場面もあると言われています。
デメリット①:移調楽器の楽譜を読むのが苦手な場合がある(固定ド思考)📉
サックスやクラリネット、トランペットなどの「移調楽器」は、楽譜に書かれた音(記譜音)と、実際に出る音(実音)が異なります。 絶対音感を持つ人は、楽譜の「ド」を見ても、頭の中では常に絶対的な「ド(C)」の音が鳴ってしまう(=固定ド思考が強い)ため、移調楽器の楽譜を読んで、頭の中で瞬時に実音に変換したり、キーに合わせて読み替えたりするのが、相対音感の人よりも苦手な場合があると言われています。「だって、『ド』は『ド』でしょ!?」ってなっちゃうんですね😅
デメリット②:少しでも音程がズレていると気持ち悪く感じる(生活音も?)🤢
メリット②の裏返しですが、音の高さに非常に敏感なため、少しでも音程がズレている音楽を聴くと、それが気になって気持ち悪く感じてしまい、純粋に音楽を楽しめないことがあります。 例えば、
- ちょっと古くてピッチが不安定なレコード
- 平均律以外の調律(民族音楽など)で演奏された音楽
- みんなで歌うカラオケ(!) などが、苦痛に感じられることもあるようです。
さらに、日常生活の中の様々な音(サイレン、電車の音、機械の動作音など)も、すべて音名として頭の中で鳴ってしまうため、それがストレスになったり、疲れてしまったりする…という方もいるようです。
デメリット③:合唱やアンサンブルで周りと合わせるのが難しい場合がある😥
合唱やアンサンブルでは、自分の音程を正確に保つことだけでなく、周りの人の音程や全体の響きに合わせて、時には微妙に自分の音程を調整することも重要になります。 しかし、絶対音感を持つ人は、自分の信じる「絶対的な正しい音程」からズレることに強い抵抗を感じることがあり、周りの音に柔軟に合わせるのが苦手な場合があります。「だって、周りの方がズレてるんだもん!」って思っちゃうわけですね。
デメリット④:相対音感が育ちにくい場合がある?🤔
これは少し議論のある点ですが、幼少期に絶対音感が非常に強く身につくと、音を常に「絶対的な高さ」で捉えるため、音と音の「関係性」や「距離(音程)」を意識する機会が減り、結果的に**「相対音感」が育ちにくくなるのではないか?という指摘もあります。 音楽活動においては相対音感が非常に重要であるため、もしこれが本当だとすると、一概にメリット**ばかりとは言えないかもしれませんね。
【!】ただし、これらのデメリットは個人差が大きい! ここで強調しておきたいのは、これらのデメリットは、絶対音感を持つ人すべてに当てはまるわけではない、ということです。絶対音感のレベルや種類、そして本人の性格や経験によって、感じ方や困り具合は全く異なります。「絶対音感がある=必ずこういうことで困る」というわけではないので、誤解しないでくださいね!
バランスが大事!絶対音感との上手な付き合い方
ここまで見てきたように、絶対音感は素晴らしい能力であると同時に、ちょっぴり不便な側面も持ち合わせている、なかなかデリケートな能力のようです。
大切なのは、「絶対音感があるから偉い/ないからダメ」と考えるのではなく、それぞれの音感の特性を理解し、バランスよく音楽と付き合っていくことかもしれません。
- 絶対音感を持っている方: その素晴らしい能力を活かしつつ、相対音感的な感覚(移動ドなど)も意識的に養うことで、さらに音楽の幅が広がるかもしれません。音程のズレへの過敏さとも、うまく付き合っていく方法を見つけられると良いですね。
- 絶対音感を持っていない方: 全く悲観する必要はありません!音楽活動において非常に重要な**「相対音感」は、トレーニングで誰でも伸ばすことができます!** むしろ、移調やアンサンブルなど、相対音感の方が有利な場面もたくさんあります。自信を持って、相対音感をどんどん鍛えていきましょう!
結局のところ、絶対音感があってもなくても、音楽を楽しむことは誰にでもできるんです!😊
絶対音感、光もあれば影もある。なかなか興味深い能力ですよね。 では、そんな絶対音感は、大人になってからでも身につけられるものなのでしょうか?次章では、その可能性について探っていきましょう!
第4章:絶対音感は大人になってからでも身につく?トレーニングの可能性
「絶対音感、やっぱりすごいなぁ…」 「私も(あるいはうちの子も)、今からトレーニングすれば、絶対音感が身につくのかな?」
特に、大人になってから音楽を始めたり、本格的に学び始めたりした方にとっては、絶対音感を後天的に習得できるのかどうか、非常に気になるところだと思います。
結論から言ってしまうと… 一般的に、大人が新たに「完璧な絶対音感」をトレーニングで身につけるのは、非常に難しい、あるいはほぼ不可能に近い、と考えられています。
「ええーっ!やっぱりダメなの!?😱」
…と、がっかりしてしまったかもしれませんね。でも、落ち込むのはまだ早い! なぜ大人の習得が難しいのか、その理由を知り、そして「じゃあ、大人でも鍛えられる音感って何なの?」ということについて、詳しく見ていきましょう!
絶対音感習得の「臨界期」とは?~幼児期の音楽体験が重要?~
第1章の「仕組み」のところでも少し触れましたが、絶対音感の習得には**「臨界期(りんかいき)」または「感受性期(かんじゅせいき)」**と呼ばれる、特定の年齢の時期が非常に重要だと考えられています。
これは、人間の脳が特定の能力を獲得するのに特に適した時期のことで、言語習得などでもよく言われますよね。 絶対音感の場合、
一般的に、幼児期、特に6歳~8歳頃まで
が、その臨界期にあたると言われています。
この時期に、
- ピアノなどの楽器に触れ、**特定の音の高さ(周波数)と、その「音名(ドレミ)」**を結びつける経験を繰り返し行う。
- 周囲の音楽環境(親が音楽家であるなど)から、常に正しい音高に触れている。
といった**適切な音楽体験(トレーニング)**を受けることで、絶対音感が自然と身につきやすいと考えられているのです。
逆に言うと、この脳が音に対して非常に柔軟な時期を過ぎてしまうと、絶対音感を新たに獲得するのは、かなり難しくなってしまう、というわけなんですね…。
大人が絶対音感をトレーニングで身につけるのは難しい?その理由
では、なぜ大人になってから絶対音感を身につけるのは、そんなに難しいのでしょうか?
- 脳の可塑性の低下: 大人の脳は、幼児期の脳に比べて、新しい神経回路を作ったり、既存の回路を大きく変化させたりする能力(=可塑性:かそせい)が低下しています。そのため、音の情報を「絶対的な高さ」として処理する特別な回路を、後から作り出すことが困難になると考えられています。
- 言語能力の影響: 私たちは成長するにつれて、音を「言語」として、つまり意味のあるカテゴリーとして認識する能力が発達します。そのため、大人になると、音を純粋な「音響的特徴(周波数)」として捉え、それを特定の「音名ラベル」と結びつける、という絶対音感的な処理がしにくくなる、という説もあります。
- 相対音感の定着: 多くの場合、大人はすでに音楽経験を通して、絶対音感とは異なる**「相対音感」(音と音の関係性で捉える力)がある程度身についています。この確立された相対音感のシステムが、新たに絶対音感**的なシステムを構築するのを妨げてしまう可能性も指摘されています。
これらの理由から、残念ながら「大人向けの絶対音感トレーニング法!」みたいなもので、誰もが簡単に絶対音感を習得できる、とは、今のところ言えないのが現状のようです…。
でも諦めないで!大人でも「疑似絶対音感」や「音感全体」は鍛えられる!
「やっぱり大人じゃ無理なのか…」 と、肩を落としたあなた!ちょっと待ってください!諦めるのはまだ早いですよ!
確かに、「生まれつき持っているような完璧な絶対音感」を大人がゼロから身につけるのは難しいかもしれません。でも、大人になってからでも、トレーニングによって向上させられる音感はたくさんあります!
- 疑似絶対音感(ぎじぜったいおんかん): これは、特定の音(例えば、自分がよく使う楽器の特定の音や、よく知っている曲の最初の音など)を「基準」として記憶し、それを手がかりにして他の音の高さを推測する能力です。例えば、「ギターの開放弦のミの音はこれくらいの高さだから、今の音はそれより少し高いからファ♯かな?」みたいに。これは、トレーニング次第でかなり精度を高めることができます!
- 音高のカテゴリー認知: ドレミ…という具体的な音名までわからなくても、「今の音は高いな」「これは中くらいの高さだな」「すごく低い音だ」といった、音高の大まかなカテゴリーを認識する能力は、トレーニングで向上します。
- そして何より!「相対音感」!!: 第2章でも強調しましたが、音楽活動において非常に重要で、かつ**年齢に関係なく、トレーニングによって誰でも、いつでも向上させることが可能なのが「相対音感」**です!音と音の関係性を正確に捉えるこの能力こそ、大人になってからでも十分に伸ばせる、あなたの強力な武器になるんです!
相対音感を徹底的に鍛えることの重要性(再確認)
だからこそ、絶対音感の習得に固執するよりも、
「相対音感を徹底的に鍛えること」
に意識を向ける方が、大人にとっては、はるかに現実的で、かつ音楽的に有益な場合が多いのです!
相対音感がしっかりしていれば、
- キーが変わってもメロディを正しく歌える(移調に強い!)
- 和音の響きやコード進行の流れを理解できる!
- 他の楽器と美しくハモれる!
- 作曲やアレンジの幅が広がる!
など、音楽を深く理解し、表現し、楽しむための能力が総合的に向上します。絶対音感がなくても、素晴らしい音楽家がたくさんいるのは、この相対音感が非常に発達しているからなんですね。
おすすめの音感トレーニング法(アプリ、ソルフェージュなど)
では、相対音感を中心に、大人でも取り組める音感トレーニングにはどんなものがあるでしょうか?
- ソルフェージュ: まさに音感トレーニングの王道!音程の聴き分け、移動ドでの視唱、聴音(旋律、和声、リズム)など、相対音感を総合的に鍛えるための練習が詰まっています。
- 聴音アプリ/Webサイト: ゲーム感覚で音程や和音の聴き分けなどをトレーニングできるツールがたくさんあります。スキマ時間に手軽にでき、自分のペースで続けやすいのが独学には嬉しい!
- 楽器練習: ピアノやギターなどで、音階(スケール)や音程、和音などを、実際に音を出しながら、その響きを耳で確認し、声に出して歌ってみる。これが理論と感覚を結びつける最高のトレーニングになります。
- 歌うこと!: カラオケでも、合唱でも、鼻歌でもOK!とにかく自分の声で音程をコントロールする練習を積極的に行いましょう!
これらのトレーニングをコツコツ続けることで、あなたの「音楽耳」は、年齢に関係なく、確実に育っていきますよ!
絶対音感が全てじゃない!トレーニングで伸ばせる相対音感を武器にしましょう! では最後に、自分に絶対音感があるのかどうか、簡易的にチェックする方法について見ていきましょう!
第5章:もしかして私も?絶対音感をチェックする簡易テスト&考え方
さて、絶対音感について色々わかってきたけど、やっぱり気になるのはコレ! 「『もしかして、私にも絶対音感、あるんじゃない…!?』」 その気持ち、すごくよくわかります!😊
この最終章では、巷でよく言われる**「絶対音感があるかどうか」を簡易的にチェックする方法**をいくつかご紹介します! ただし!あくまで「お遊び」というか、「目安」程度に考えて、軽い気持ちで試してみてくださいね!そして、その結果に一喜一憂しないための、大切な考え方についてもお伝えします。
「自分に絶対音感があるか知りたい!」簡易的なチェック方法
【!】注意!【!】 これから紹介する方法は、あくまで簡易的なチェックであり、医学的・科学的に厳密なテストではありません。 正確な絶対音感の有無やレベルを知りたい場合は、音楽教室や研究機関など、専門家によるしっかりとした検査が必要です。自己判断は禁物ですよ!
…という注意点を踏まえた上で、レッツ・トライ!
チェック①:楽器で鳴らされた単音の音名を当てる
これが一番ポピュラーなチェック方法かもしれませんね。
【やり方】
- 協力者(家族や友人など)に、ピアノやキーボードなどの音程が正確な楽器を用意してもらいます。(スマホのピアノアプリでもOK!)
- あなたは鍵盤を見ないように後ろを向くか、目隠しをします。
- 協力者に、ランダムに単音をポーン!と弾いてもらいます。(最初は白鍵だけでもOK!)
- あなたは、**聴こえた音の「音名(ドレミファソラシド、あるいはCDEFGAB)」**を答えます。
- これを何度か(10回~20回くらい?)繰り返し、どれくらい正解できたかを見てみます。
【目安】 もし、ほとんどの音を迷わず、瞬時に、正確に言い当てることができれば、あなたは絶対音感を持っている可能性が高いと言えるかもしれません!✨ 逆に、「うーん、今の音はさっきの音より高いけど…何の音だろう?」と考えてしまう場合は、相対音感を使って判断している可能性が高いです。
チェック②:生活の中の音(救急車、踏切など)の音名を当てる
楽器の音だけでなく、**日常生活にあふれる様々な「音」**が、特定の「音名」として聴こえるかどうかも、絶対音感の一つの特徴と言われています。
【試してみて!】
- 救急車のサイレン🚑:「ピーポーピーポー」が、特定の音程関係(例:「シ♭」と「ソ」の繰り返し)として、常に同じ高さに聴こえますか?
- 踏切の音:「カンカンカン…」という音が、特定の音名(例:「ファ♯」?)に聴こえますか?
- 時報:「ピッ、ピッ、ピッ、ポーン」の「ポーン」は何の音に聴こえますか?(これは「ラ(A)」の音=440Hzに近いことが多いです)
- 家電の音:電子レンジの終了音、電話の呼び出し音、冷蔵庫の動作音…これらが特定の音名として認識できますか?
もし、これらの生活音が、常に(あるいは多くの場合)特定の音名として、色が付いているように感じられるなら、それも絶対音感を持っているサインかもしれません。
結果に一喜一憂しない!絶対音感があってもなくても音楽は楽しめる!
さて、簡易チェック、試してみましたか? 結果はどうでしたか?
「やったー!全部わかった!私、絶対音感あったんだ!」 「うーん、全然わからなかった…やっぱり私には才能ないのかな…」
…と、結果を見て喜んだり、落ち込んだりしているかもしれませんね。
でも、ここで一番伝えたい大切なこと! それは、**この簡易チェックの結果に、一喜一憂する必要は全くない!**ということです!
なぜなら…
- 絶対音感があっても、それだけで素晴らしい音楽家になれるわけではない! (第3章のデメリットも思い出して!)
- 絶対音感がなくても、音楽を深く理解し、心から楽しむことは、誰にでもできる!
- 音楽活動において、絶対音感以上に重要とされる場面が多い「相対音感」は、トレーニングで伸ばせる!
そう、絶対音感は、数ある音楽能力の一つに過ぎません!持っていれば便利な場面もあるかもしれませんが、それが音楽を楽しむ上での「必須条件」では決してないんです。
大切なのは、自分に合った方法で「音楽的な耳」を育てること
絶対音感があるかないか、それは個性の一つ。 それよりもずっと大切なのは、
「自分自身の耳と向き合い、自分に合った方法で、音楽を豊かに感じ取れる『音楽的な耳』全体を、楽しみながら育てていくこと」
ではないでしょうか?
- 相対音感を鍛えて、メロディやハーモニーの関係性を深く理解する。
- リズム感を養って、グルーヴを感じながら音楽に乗る。
- 和音の響きを聴き分けて、曲の色彩や感情を感じ取る。
- 様々な楽器の音色の違いを楽しむ。
音楽を楽しむための「耳」の能力は、絶対音感以外にもたくさんあります。そして、その多くは、トレーニングによって向上させることが可能です!
絶対音感の有無にこだわるのではなく、ぜひ、あなた自身のペースで、あなたの好きな音楽を通して、豊かな「音楽耳」を育てていきましょう!
絶対音感の謎、少しは解けたでしょうか? これで絶対音感についての解説は終わりです!さあ、最後のまとめで、今回の旅を締めくくりましょう!
まとめ:絶対音感は一つの才能。でも、それが音楽の楽しさの全てじゃない!
いやはや、ミステリアスな「絶対音感」の世界を探る旅、これにて全行程終了です!最後までお付き合いいただき、本当に、本当にありがとうございました!😭🙏
「絶対音感って、結局なんなの?」 「相対音感とはどう違うの?」 「メリットだけじゃなくて、デメリットもあるんだ…」 「大人になってからのトレーニングは難しいのか…」 「チェックしてみたけど、うーん…」
などなど、この記事を通して、あなたの絶対音感に対する「?」が、少しでも「!」に変わっていたら、ナビゲーターとしてこんなに嬉しいことはありません!✨
最後に、この絶対音感探求の旅で明らかになった重要なポイントを、ぎゅぎゅっとまとめておきましょう!
【絶対音感の取扱説明書:要点まとめ】
- 絶対音感とは?: 音の絶対的な高さを、他の音と比較せずに音名で認識するレアな能力!(第1章)
- 相対音感との違い: 絶対座標 vs 相対距離!役割が異なり、相対音感はトレーニングで誰でも伸ばせる!(第2章)
- メリット&デメリット: 耳コピ楽々?でも移調やズレが苦手?光もあれば影もある!(第3章)
- 大人でも身につく?: 完璧な絶対音感は難しいが、相対音感など「音楽的な耳」はいつでも育てられる!(第4章)
- チェック方法は?: あくまで目安!結果に一喜一憂せず、大切なのは…?(第5章)
そう、第5章でもお伝えしたように、絶対音感は確かに興味深く、特定の場面では便利な才能かもしれません。でも、それが音楽能力の全てではなく、音楽を楽しむための必須条件でも決してない、ということを、ぜひ覚えておいてください。
大切なのは、絶対音感があるかないか、ということよりも、
あなた自身の耳と心で、音楽を豊かに感じ取り、表現し、楽しむこと!
そのために、あなたができることはたくさんあります!
- 絶対音感の有無は気にせず、まずはトレーニングで確実に伸ばせる**「相対音感」を鍛えることに集中してみませんか?(音程の聴き分け**、移動ドでの視唱など)
- 自分の音感の得意なところ、苦手なところを意識しながら、いろんな音楽を聴いたり、楽器を演奏したり、歌ったりしてみませんか?
- 何よりも、難しく考えすぎず、ただただ好きな音楽を心ゆくまで楽しむ時間を大切にしませんか?
あなたの音楽ライフを本当に豊かにするのは、音感の種類ではなく、あなたの音楽への愛情と、「もっと知りたい!」「もっと楽しみたい!」という探求心のはずです。
絶対音感って、なんだかんだ言ってもやっぱり気になる、面白いテーマですよね。私もこの記事を書きながら、改めて音感の不思議さ、奥深さを感じました。絶対音感があってもなくても、それぞれの方法で、音楽の楽しみ方は無限大に広がっています!
この記事が、あなたが絶対音感について正しく理解し、音感への囚われから少し自由になって、もっとのびのびと音楽と関わっていくための、小さなヒントになれたなら嬉しいです。
お礼の言葉
改めまして、このちょっぴりマニアックで、時に脳科学(?)にまで足を踏み入れた「絶対音感」の世界への探求に、最後までお付き合いいただき、本当に、本当にありがとうございました!
あなたの「知りたい!」という純粋な好奇心が、私にこの記事を書き上げるエネルギーを与えてくれました。心からの感謝を込めて。
絶対音感があってもなくても、あなたの素晴らしい「音楽耳」が、これからたくさんの美しい音やハーモニー、リズムを感じ取り、あなたの人生をさらに豊かに彩ってくれることを、心から応援しています!🏳️🌈🎶
ぜひこれからも、あなたの耳と心を信じて、音楽の世界を思いっきり楽しんでくださいね! 本当にありがとうございました!😊